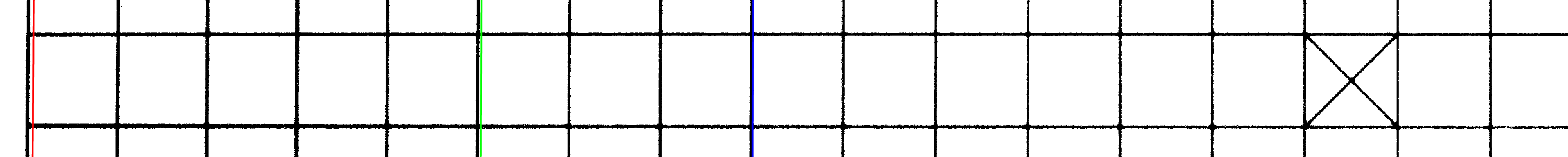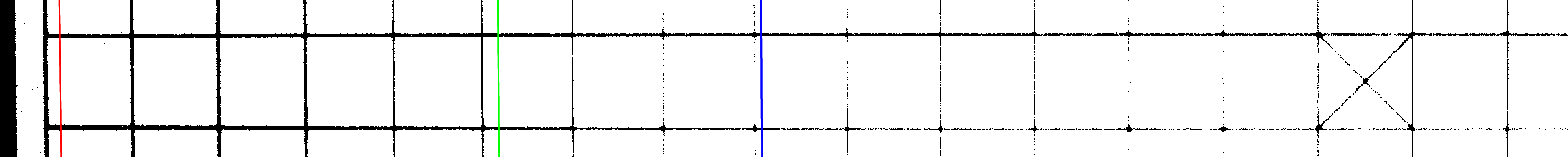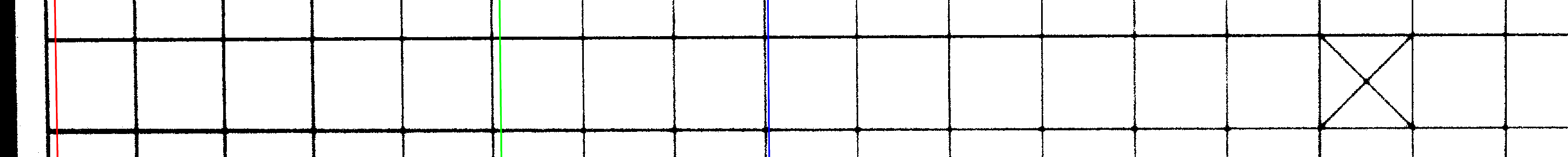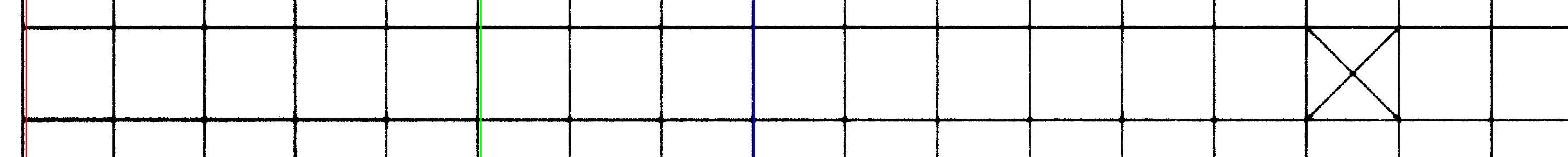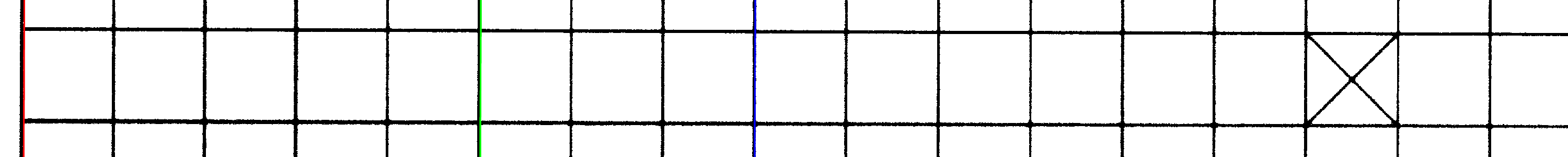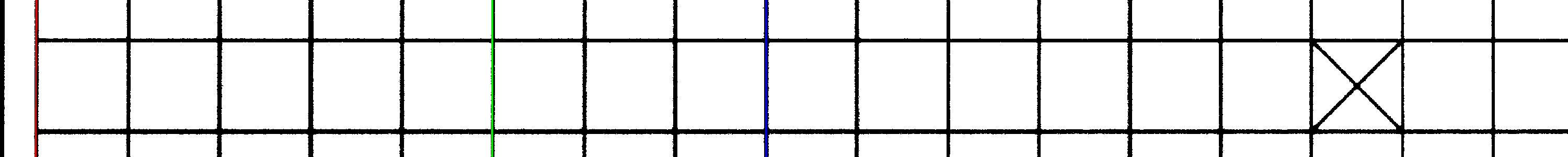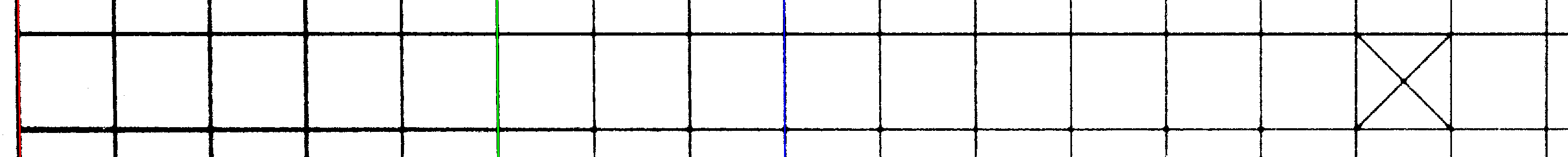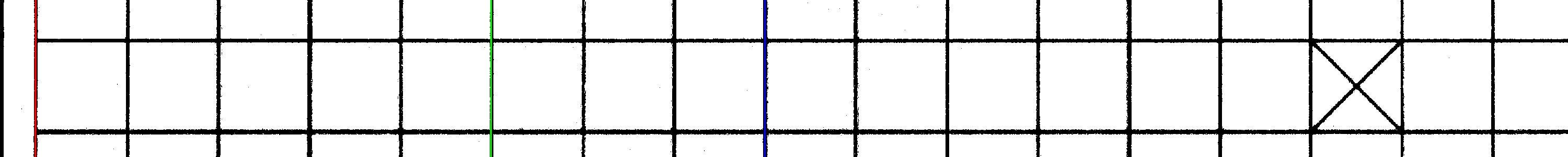目指せ!アマチュアカメラマン!
題 『満月』

Olympus E-M1、Minolta500mm、MAF-M4/3。ISO200、500mm、F8、SS1/320、自動WB。
RAW現像にて、トリミング、コントラスト+2、ノイズフィルタ弱。2023,03,07撮影。
・ 「 https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/U/UAP14475/20221114/20221114201545.jpg 」
Canon EOS 7D、COSINA28-210mm。ISO400、210mm、F11、SS0.8、自動WB。
RAW現像にて、トリミング、輝点除去。
・ 「 https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/U/UAP14475/20220916/20220916203056.jpg 」
Canon EOS 5D、EF28-135mm。ISO400、135mm、F14、SS1/1000。
コツコツ集めた(?)カメラを一覧にしてみました。
スマホでパシャリ、なんてけしからん! みんなで一眼レフ・ミラーレスを買おう!
お手頃なAPS-Cサイズセンサー搭載の中古品が君を待っている・・・!
- マイクロフォーサーズマウント
- OLYMPUS PEN Lite E-PL6
- Panasonic LUMIX DMC-GH1
- OLYMPUS OM-D E-M1★お気に入り★
- ズームレンズ(パナソニック軍団)
- Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-FS12032-S)★お気に入り★
- Panasonic LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8/POWER O.I.S (H-HS35100)
- Panasonic LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 /MEGA O.I.S. (H-FS100300)
- ズームレンズ(オリンパス軍団)
- 単焦点レンズ
- Eマウント・フルサイズ(FEマウント)
- Eマウント・APS-C
- SONY α NEX-6
- 単焦点レンズ
- Carl Zeiss Touit 2.8/12
- SIGMA Art 30mm F2.8 DN (A013)
- Aマウント
- EF/EF-Sマウント・APS-C
- Canon EOS 10D
- Canon EOS 7D★お気に入り★
- SIGMA SD1 Merrill EFマウント改造型
- 広角ズームレンズ
- SIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM★お気に入り★
- 標準ズームレンズ
- TAMRON SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] (B005E)
- SIGMA 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM
- Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM
- フラッシュ(ストロボ)
- Canon SPEEDLITE 580EX II
- EFマウント・フルサイズ
- SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM 【掲載予定・参考リンク】
- SIGMA MINI ZOOM MACRO 28-80mm F3.5-5.6
- SIGMA MINI ZOOM MACRO 28-80mm F3.5-5.6 II
- SIGMA MINI ZOOM MACRO 28-80mm F3.5-5.6 HF
- Canon EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM
- COSINA 28-210mm MC 1:4.2-6.5 ASPHERICAL IF
- Canon EF75-300mm F4-5.6 II USM
- Tokina EMZ130AF 100-300mm F5.6-6.7
- 単焦点レンズ
- マウントアダプター&テレコンバーター
- VILTROX JY-43F
- K&F Concept MAF-M4/3
- Commlite EF-NEX 【掲載予定】
- Kenko DIGITAL TELEPLUS PRO300 1.4X DG
- Kenko DIGITAL TELEPLUS PRO300 2X DG
- フィルター
- クローズアップレンズ
- レンズプロテクター
- メモリーカード
- WesternDigital SiliconDrive 1GB PATA (SSD-C01G3565)
- Sandisk Extreme コンパクトフラッシュカード
- Sandisk Extreme Pro コンパクトフラッシュカード
- 思い出のコンデジ
- 思ったこと
- 便利なリンク集
- 便利なリンク集(お買い物用)
■マイクロフォーサーズマウント
沈胴構造を採用しているレンズも多いため、装備の小型化・軽量化に貢献する。
センサーサイズが小さいため同じ画角ではボケが小さく、パンフォーカスになりやすい。
焦点距離を2倍にすると35mm換算の画角が求められる。(例:M4/3の14mm=35mm換算で28mm)
| OLYMPUS PEN Lite E-PL6 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
( 撮影 : α57 + SAL1855 ) SILKYPIX Pro11、フラッシュON |
|||||||||||||||||||||||
クリックして展開2013年発売のマイクロフォーサーズ(M4/3)サイズイメージセンサー搭載ミラーレスカメラ。 M4/3規格らしい小型軽量なボディは一眼レフよりコンデジに近い使用感を与える。 カラーバリエーションはホワイト、シルバー、レッド、ブラックとオシャレな多色展開。 ホットシューには専用ストロボのほか、別売のEVF「VF-04」などに対応している。 ボディ内2軸手ブレ補正を搭載しているため、レンズ側に手ブレ補正機能がなくても安心。 ただし効果のほどは撮影結果を見るまで分からない。(ムービーモードではライブビューで確認できる) 使ってみた感じではTAMRON・17-50やSIGMA・18-50のレンズ内手ブレ補正とだいたい同じ程度。 また、Panasonicの「Dual I.S.」の説明文には以下のようにある。 ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)だけでは焦点距離が伸びるにつれ、補正角が大幅に減少していきます。「Dual I.S.」による補正では、中望遠域はもちろんのこと、B.I.S.補正だけでは、補正効果が得られにくい望遠域でも手ブレを補正することが可能となります。
( 出典 : https://panasonic.jp/dc/lens/dual_is/about.html ) つまるところ、ボディ内手ブレ補正は焦点距離が伸びるほど効果が低下するのである。 ある程度大きくズームさせたい場合はレンズ内手ブレ補正があるものが望ましいだろう。 なお協調動作は(たぶん)非対応。 ■オートフォーカス、動画撮影 オートフォーカスはコントラストAFではあるものの、EOS7Dのライブビューと比べると非常に速い。 動画撮影でもコンティニュアスAFが選択可能。これもなかなか悪くない速さで、かつ迷いが少ない。 30fpsでしか撮影できない点が玉に瑕だがビデオカメラを別途用意できない場合には使えるだろう。 なお、動いている被写体に対する性能は未確認である。(ある程度の速度までならイケそうだが・・・) ■ファインダー、背面液晶 小型モデルのためファインダーは内蔵しないが、別売オプションとして数種類のEVFが存在する。 EVFを装着しない場合は46万画素の背面液晶で撮影を行うことになる。色味は結構良いと思う。 晴天時に屋外撮影を行う場合は外光により視界不良になりやすい。 液晶パネルは上下には自由に動かすことができるが、左右に回転させることはできない。 後継のE-PL7と違って、液晶パネルを前に向ける場合は上側に飛び出させるため三脚との相性が良い。 ちなみに、かわいらしいデザインの割に液晶を支えるアームはゴツくて固い。内剛外柔というやつだろうか? 二軸の電子水準器は画面端に棒状で表示され、視界を広く取れる。 ■シャッター音
■現像設定、購入メモ、リンク ピクチャーモードはNaturalに彩度-1としている。(彩度を下げない場合は赤が強め) ISO感度は800で常用。ISO1600からは輪郭が怪しい。屋外ではISO400。 自室で撮影する際はISO800、 リコレにて、2022,10,01注文⇒2022,10,02発送⇒2022,10,04受取。 本体18,980円+送料550円。中古品C。完品。 レンズキットなので M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R が付属した。 購入時より電池蓋のツメの部分が片方欠損している。(状態説明には書かれていなかったのだが・・・) この状態でもフタは閉まるし、撮影動作に影響はないものの、フタを開けた際にポロリすることがある。 そもそもフタのツメがプラスティック製なのがいただけない。ヒンジくらい金属にできただろうオリンパス? ついでに電子水準器が狂っていた。・・・が、メニューから調整できるので助かった。 ちなみに着脱式のグリップMCG-4のネジは10円玉で回せる。(コインボルト) ・ 「 https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/epl6/ 」 (公式サイト) ・ 「 https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/digital-pen/e-pl6/ 」 (公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/602213.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B00CPLPZHK/ 」(Amazon) | ||||||||||||||||||||||||
[TIPS] イメージセンサーの製造元当時のニュースリリースによると、E-PL6はE-M5と同じセンサーを使用しているという。 当社ミラーレス一眼カメラ最上位機である「OLYMPUS OM-D E-M5」に搭載された1605万画素 Live MOS センサーと画像処理エンジン「Truepic VI」を「OLYMPUS PEN Lite E-PL6」にも採用しました。
( 出典 : https://www.olympus.co.jp/jp/news/2013a/nr130510epl6j.html ) そして、E-M5のセンサーの製造元は以下の記事によるとSONY製らしい。あっ(察し) ・ 『 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/544400.html 』 オリンパス製ミラーレスのイメージセンサーの製造元については他にもモロモロの情報が見つかる。 オリンパス自身があまり公式発表をしないため尚更話題になりやすいのかもしれない・・・。 ( M4/3で半ば運命共同体のパナソニックを捨ててSONYに鞍替えはイカんでしょ ) ・ 『 https://digicame-info.com/2017/04/e-m1-mark-ii-imx270.html 』 | ||||||||||||||||||||||||
| Panasonic LUMIX DMC-GH1 | ||||||||||||||||||||||||
 |
( 撮影 : α57 + SAL1855 ) SILKYPIX Pro11、フラッシュON |
|||||||||||||||||||||||
クリックして展開2009年発売のマイクロフォーサーズ(M4/3)サイズイメージセンサー搭載ミラーレスカメラ。 144万画素のEVF(または「ライブビューファインダー」)、内蔵ストロボ、大型グリップを備え、 サイズは一眼レフカメラより一回り小ぶりながらも機能面では見劣りしない高性能機となっている。 カラーバリエーションはブラック、レッド、ゴールドとオシャレな多色展開。 ■オートフォーカス、動画撮影 オートフォーカスはコントラストAFではあるものの、EOS7Dのライブビューと比べると非常に速い。 動画撮影ではコンティニュアスAFのみ利用可能。1280x720pxでは悪くない速さで動く。 1920x1080pxではセンサー出力24pの60iでしか撮影できないが、 1280x720ではセンサー出力60pで撮影できるため、滑らかな映像を記録できる。 ■ファインダー、背面液晶 搭載するEVFは画素数こそ144万画素と悪くないのだが、フィールドシーケンシャルカラー方式らしく色割れする。 視線を動かした際に画面がRGBで分光しているように見える。動く被写体を追いかける場合はストレスになるだろう。 ・ 『 LUMIX DMC-G1 ~ G1 が奏でるレンズ交換式カメラの新しい愉しみ~ 』 ・ 『 フィールド・シーケンシャル・カラー表示における色割れと視者視力および色表示周波数の関係 』 そして暗い場所を見た際にはフレームレートが低下し、だいぶカクカクになってしまう。 光学ファインダー(OVF)に慣れているほどこの欠点は目に付くだろう。・・・ファインダーなだけに。 一方、背面液晶パネルは解像度こそ46万画素ながら大きく見やすい。角度もスムーズに調整できる。 そしてひっくり返して折りたためばキズ・ヨゴレも防止できる。気兼ねなく鼻を押し付けることも可能。 よく考えるとビデオカメラの液晶が横向きについているだけなのだが、E-PL6のアレより使いやすい。 ■シャッター音
■現像設定、購入メモ、リンク 保存したRAWデータは(少なくともSilkyPixSEで現像する場合)撮影時に設定した画面比率で現像される。 E-PL6のように3:2で撮影したものを後から4:3で現像したりはできない模様。 フィルムモードは「スムーズ」にしている。(ほぼRAW現像必須) ISO感度は800で常用。 自室で撮影する際はISO800、F5.6、SS1/15にしている。 なお、電池蓋のヒンジは金属製であるようだった。E-PL6のようにはならないだろう。 Amazonにて、2022,11,23注文⇒2022,11,24発送⇒2022,11,26受取。 本体7,300円+送料無料。中古品(良い)。ズームキットの外箱、取扱説明書、ケーブル3本、充電器が付属。 三脚座の周りが変色している。そして説明文にはなかったのだが香水のニオイが付いている。 ・ 「 https://panasonic.jp/dc/p-db/DMC-GH1.html 」 (公式サイト) ・ 「 https://news.panasonic.com/jp/press/jn090518-1 」 (公式プレスリリース) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2009/05/13/10814.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://ja.wikipedia.org/wiki/パナソニック_LUMIX_DMC-GH1 」(Wikipedia) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01M7T851O/ 」(Amazon) | ||||||||||||||||||||||||
[TIPS] PCでのRAW現像に関して (SILKYPIX Developer Studio SE)DMC-GH1には専用のRAW現像ソフトとして 「 SILKYPIX Developer Studio SE 」 が用意されている。 ただし、無料なのは SE と付いているエディションで、これが付いていないものは有料版。 有料版ではPanasonic製でないカメラのRAWデータにも幅広く対応しているという。 SilkyPixSEはバージョン8.0.14.1の時点でWindows8.1/10/11に対応している。 実際に使ってみると、CanonのDPPやOlympusのWorkspaceに比べてだいぶ軽い印象。 ただ、インターフェースが複雑なうえにアイコンだらけで使い方が分かりにくいと感じる。 このソフトを初めて使う場合は公式サイトの「マニュアル」のページを開いておく必要があるだろう・・・。 注意が必要なのは このソフトの標準設定はカメラボディの標準設定とは異なる ということ。 DPPやWorkspaceではRAWファイルを読み込んで編集せずにそのまま出力すると、 ボディで現像したものと(ほぼ)同じ画像ファイルを得ることができるが、SilkyPixではそうならない。 このため、ボディ現像とSilkyPix現像の写真を並べると写りが違ってしまう。 ホワイトバランスはさすがに引き継がれるものの、フィルムモードは完全に無視されてしまうため、 色合い、シャープネス、ノイズ除去、といった部分についてはSilkyPixで再設定する必要がある。 現在のところは以下の設定で現像している。( 書いていない部分は標準のまま )
・ ホワイトバランス どうもDMC-GH1は黄緑っぽくなりやすいようなので赤味が出るように調整している。 ボディ内の「ホワイトバランス微調整」であらかじめ調整しておくことが理想だが、 SilkyPixの色温度・色偏差で後からでも調整できる。 なお、AWBやプリセットWBで屋外撮影したものは調整なしでも良いと思う。 ・ 調子 もとからコントラストが低くなりやすいようなので「標準」かそれ以上しか使わない。 「硬調」でさえ他社の標準設定よりおとなしいコントラストで仕上がる。 上の設定ではコントラストが増強され、特に影が濃くなる。若干キツいかも・・・。 ・ カラー なるべく現実的な色になるようにしている。「忠実」はまさにピッタリ。 色表現は「フィルム調A」も悪くないと思ったが、結局「標準色」のままにしている。 ・ シャープ なんとなくノーマルシャープのほうが(人工物の場合は)良い気がしたので変えている。 数値の部分は標準のままでいいと思う。 ・ ノイズリダクション 偽色抑制を上げたほうが変な色づきがなくなるものの、 細かな模様の入った被写体に対して数値を上げすぎると色が飛んでしまうため注意が必要。 ⇒ 「ナチュラルシャープ」のせいだったようだ。「ノーマルシャープ」ならだいぶマシになった。 ■リンク ・ 「 SILKYPIX Developer Studio SEバージョン 」 (公式サイト) | ||||||||||||||||||||||||
| OLYMPUS OM-D E-M1 | ||||||||||||||||||||||||
 |
( 撮影 : α57 + SAL1855 ) SILKYPIX Pro11、フラッシュON |
|||||||||||||||||||||||
クリックして展開2013年発売のマイクロフォーサーズ(M4/3)サイズイメージセンサー搭載ミラーレスカメラ。 オリンパスの当時のフラッグシップ機であり、当時最高峰の技術が惜しみなく投入されている。 像面位相差AF、倍率色収差補正、5軸手ブレ補正、236万ドットEVF、大型グリップ、防塵防滴構造、などなど。 カラーバリエーションはブラックとシルバーの2色展開。 E-M1からはオリンパス・パナソニック両社のレンズで倍率色収差のデジタル補正が可能となっている。 ・ 『 価格.com - 『他社レンズの収差補正』 オリンパス OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ のクチコミ掲示板 』 ・ 『 オリンパスOM-D E-M1はこれまでのm4/3機でベストの画質 - デジカメinfo 』 インタビュー記事によると、オリンパス製のフォーサーズレンズ(MじゃないZUIKO)のデータも収録、 イメージセンサーはローパスフィルターレスになっているとされている。 ・ 『 インタビュー:「OLYMPUS OM-D E-M1」の進化に迫る - デジカメ Watch Watch 』 ■オートフォーカス、動画撮影 オートフォーカスは新たに採用された像面位相差AFと、従来からのコントラストAFを併用しており、 取り付けるレンズと、シングルAF(S-AF)かコンティニュアスAF(C-AF)かで自動的に切り替わる。 ・ 『 https://www.jstage.jst.go.jp/article/photogrst/77/3/77_213/_pdf 』
像面位相差AFは「ハイブリッドCMOS AF」などと同じく、位相差検出用の画素を埋め込む形式で、 上の論文に写真付きで掲載されている通り、4x4ピクセルに1つの間隔で配置されている。 ただ、M4/3+S-AFで使う場合はコントラストAFになるので使い方によっては恩恵が感じられない。 もとよりM4/3レンズはコントラストAFでも高速なので、4/3レンズやC-AF向けの強化と考えていいだろう。 ■ファインダー、背面液晶 EVFは236万ドットと十分に精細だが、それ以上に色割れがないため非常に見やすい。 もしやフィールドシーケンシャルカラー方式ではないのでは、と思うが公式情報は見つけられなかった。 このほか「キャッツアイコントロール」や「OVFシミュレーション」といった機能で自然な「見え」を実現している。 特に後者はどういう理屈かは分からないが、見ていて違和感のない映像になるので気に入っている。 ファインダーには2軸(ピッチ方向・ロール方向)の水準器のほか、 表示スタイルによってはシャッター半押し時に1軸(ロール方向)の水準器を表示させることもできる。 特に後者は視界を遮ることなく水平にできるため非常に便利だと感じている。 背面液晶はファインダーよりキレイに見えるが、残念ながらひっくり返すことができない。 そのためローアングル・ハイアングルでの撮影は可能なものの、セルフィーには対応しない。 そんなことに使うカメラではない、ということかもしれないが、せっかくならできるようにしてほしかった。 ■操作系統 もともとボタンの多いE-M1だが「2x2ダイヤルコントロール」というレバー切り替え式の操作系統も備えており、 「1」の位置では「絞り」と「シャッタースピード」、「2」の位置では「ISO感度」と「ホワイトバランス」をダイヤル制御できる。 機能がどう切り替わるかは覚えなくてはいけないが、慣れればなかなか便利に操作できる。 オリンパス機らしくボタン機能の割り当てもかなり柔軟に変更できるため、自分の使いやすいようにカスタムできる。 現在のところは以下のように機能を割り当てて使用している。 ・ Fn-1 ・・・ 拡大 ・ Fn-2 ・・・ ピーキング ・ AELボタン ・・・ OVFシミュレーション ・ WBボタン ・・・ ブラケット撮影切り替え ■現像設定、購入メモ、リンク (追記予定) Amazonにて、2023,03,01注文⇒2023,03,04発送⇒2023,03,05受取。 本体35,000円+送料無料。中古品(良い)。BCL-1580セット。おそらくCD-ROMのみ欠品。 説明文にはなかったのだが香水のニオイが付いている。 ・ 「 http://olympus-imaging.jp/product/dslr/em1/ 」 (公式サイト・リンク切れ) ・ 「 https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/digital-om/e-m1/ 」 (公式サイト) ・ 「 https://www.olympus.co.jp/jp/news/2013b/nr130910em1j.html 」 (公式プレスリリース) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/616624.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://ja.wikipedia.org/wiki/オリンパス・OM-D_E-M1 」(Wikipedia) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00NED5VDG/ 」(Amazon) | ||||||||||||||||||||||||
| ズームレンズ(パナソニック軍団) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
左から、 ・ Panasonic 12-32mm F3.5-5.6 (H-FS12032-S) ・ Panasonic 35-100mm F2.8 (H-HS35100) ・ Panasonic 100-300mm F4.0-5.6 (H-FS100300) | |||||||||||||||
| Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-FS12032-S) | ||||||||||||||||
| 【フィルター径φ37mm】 【手ブレ補正あり】 【寸法(沈胴)φ55.5x24mm】 【重量70g】 【インナーフォーカス】 | ||||||||||||||||
【解像力検証】 16MP
画面端以外は十分写る。 M4/3レンズは絞っても解像力が向上しにくいため、おそらくこれでピーク性能。 ・ 「 (独立記事作成予定) 」 | ||||||||||||||||
クリックして展開2013年に発売された標準ズームレンズ。いわゆる「パンケーキレンズ」。 沈胴構造を採用しており、撮影しない時はズームリングを操作することで短くできる。 電動ズーム並みの小ささだがズームは手動で、さらに手ブレ補正まで搭載している。 代わりにフォーカスリングが完全に無くなってしまった。 ■光学性能 このレンズはキットレンズの一つではあるものの、写りについては十分優秀と感じられる。 広角端での画面端の解像力はちょっと物足りないが、これは同価格帯のレンズではよくあることだと思う。 このサイズでキチンと写るのならもう文句は付けられないだろう。 ところが、「 オリンパス製カメラボディでは色収差補正が効かない 」 というクチコミは本当だったらしく、 E-PL6での撮影時には広角端での色収差(パープルフリンジ)が結構気になった。 ・ 「 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000586788/SortID=22977311/ 」 オリンパスの場合は 「 TruePicVII 」 搭載のモデルから倍率色収差補正に対応しているらしい。 そのためE-PL7やE-M1などもう少し新しいモデルであれば補正してもらえる可能性がある。 なお、倍率色収差補正非対応の場合でもRAWで保存している場合は「OM Workspace」から手動で補正できる。 ・ 「 http://okachan.blue.coocan.jp/digital/truepic/truepic.html 」 ・・・ TruePicの世代ごとの違い パナソニック製の「Dual I.S.」対応ボディに取り付けた場合は手ブレ補正の協調動作が可能であるという。 一方、オリンパス製ボディの場合は協調動作できない。(同じM4/3なのになぜ互換性を持たせない・・・?) E-PL6装着時は標準でボディ側の手ブレ補正のみが作動するが、カスタムメニューから 「レンズ手ぶれ補正優先」を「On」にするとレンズ側の手ブレ補正のみを作動させることができる。 ■外観など 沈胴状態では全長24mmという驚異的な短さにまで短縮される。 外装はツヤ消しの金属製だが、重さが70gしかないため重厚感はあまり感じない。 そして内筒はプラスティック製のようにも見える。 沈胴状態を除くと、ズームリングが23mmくらいのところで鏡筒が最も短くなる。 SIGMA・28-80mmやOLYMPUS・14-42mmと同じく2群ズームと思われる。 繰り出した状態での長さはOLYMPUS・14-42mmより短い。 なお、公式サイトでは「金属マウント」と表示されているが、手元の個体は「プラマウント」であった。 ウワサによるとキットレンズとして付属する分はプラマウントらしい・・・が、真偽不明である。 ■購入メモ、リンク Amazonにて、2022,10,10注文⇒2022,10,11発送⇒2022,10,12受取。 本体12,500円+送料無料。中古品(良い)。フロント・リアレンズキャップ付属。 この個体はプラマウント仕様のものだった。ウワサによるとキットレンズのものはこうらしい。 ・ 「 https://panasonic.jp/dc/products/g_series_lens/lumix_g_vario_12-32.html 」(公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/619801.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://kakaku.com/item/K0000586789/ 」(価格.com) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00FYK2PYK/ 」(Amazon) | ||||||||||||||||
[TIPS] 色収差&歪曲収差補正(OM Workspace)E-PL6などの古いオリンパス製ボディは色収差補正に対応していないものの、 純正のRAW現像ソフトウェア「OM Workspace」から手動で補正できる。 また、ボディ内補正では取りきれていない歪曲収差を完全に取り除くことも可能。 以下は私が独自に検証した補正値。だいたい消えると思うが最終的には目視確認、しよう(提案)
| ||||||||||||||||
| Panasonic LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8/POWER O.I.S (H-HS35100) | ||||||||||||||||
| 【フィルター径φ58mm】 【手ブレ補正あり】 【寸法φ67.4x99.9mm】 【重量360g】 【インナーフォーカス】 【インナーズーム】 【防塵防滴】 | ||||||||||||||||
クリックして展開2012年に発売された望遠ズームレンズ。LUMIXの上位グレード「Xレンズ」に位置付けられている。 開放F値をF2.8通しとしつつ、全長100mm程度のインナーズームとしているため取り回しは良好。 望遠端が換算200mmとやや短いことを除けば弱点のない、非常に上質なレンズに仕上がっている。 後継モデルは「H-HSA35100」。そのさらに後継モデルの「H-ES35100」も存在する。 専用フードには型番の記載がないが、「VYC1085」という名称で単品販売されていたりする。 ■光学性能 (評価中) ■外観など (評価中) ■購入メモ、リンク Amazonにて、2024,03,02注文⇒2024,03,07発送⇒2024,03,08受取。 本体52,980円+送料無料。中古品(非常に良い)。おそらく完品。 ・ 「 https://panasonic.jp/dc/p-db/H-HS35100.html 」(公式ページ) ・ 「 https://news.panasonic.com/jp/press/jn120918-1 」(公式プレスリリース) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B009CNILX4/ 」(Amazon) | ||||||||||||||||
| Panasonic LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 /MEGA O.I.S. (H-FS100300) | ||||||||||||||||
| 【フィルター径φ67mm】 【手ブレ補正あり】 【寸法φ73.6x126mm】 【重量520g】 【インナーフォーカス】 | ||||||||||||||||
クリックして展開2010年に発売された超望遠ズームレンズ。 換算200-600mmという長い焦点距離を持ちながらも全長126mmと携行しやすいサイズに収まっている。 後継モデルは防塵防滴性能が追加された「H-FSA100300」。 専用フードには型番の記載がないが、「VYC1016」という名称で単品販売されていたりする。 ■光学性能 (評価中) ■外観など (評価中) ■購入メモ、リンク ヤフオクにて、2024,03,09即決落札⇒2024,03,10発送⇒2024,03,12受取。 本体26,500円+送料780円。中古品。おそらく完品。 ・ 「 https://panasonic.jp/dc/p-db/H-FS100300.html 」(公式ページ) ・ 「 https://news.panasonic.com/jp/press/jn100921-2 」(公式プレスリリース) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B0043XY8YO/ 」(Amazon) | ||||||||||||||||
| ズームレンズ(オリンパス軍団) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
左から、 ・ OLYMPUS 14-42mm F3.5-5.6 II R ・ OLYMPUS 40-150mm F4.0-5.6 R | |||||||||||||||
| OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R | ||||||||||||||||
| 【フィルター径φ37mm】 【手ブレ補正なし】 【寸法(沈胴)φ56.5x50mm】 【重量113g】 【インナーフォーカス】 | ||||||||||||||||
クリックして展開2011年に発売された標準ズームレンズ。「R」と付かないモデルはデザイン変更前のもの。 沈胴構造を採用しており、撮影しない時はズームリングを操作することで短くできる。 専用フードはLH-40。フィルター枠外周部のカバーを外して取り付けできる。 ■光学性能 キットレンズながら写りは十分で、E-PL6などのM4/3ボディはデジタル補正対応なので歪みも少ない。 某海外サイトによると開放絞りからMTFはあまり変化しないものの、色収差はF8までの間で逓減するらしい。 もとよりあまり明るくはないのでPモードでカメラにお任せしちゃっていいかもしれない。 オートフォーカス中でも動作音がほとんどしないほどの静粛性を持つほか、 バイワイヤ方式を採用しているためマニュアルフォーカスが有効でない場合は回しても反応せず、 逆にオートフォーカスならフォーカスリングは一切回らない。ちょっと不思議なレンズである。 ちなみにフォーカスリングの回し心地は結構良い。そして無限に回るので遊べる。 ■外観など (沈胴状態を除くと)ズームリングが20mmくらいのところで鏡筒が最も短くなる。 SIGMA・28-80mmと同じく2群ズームと思われる。 ■購入メモ、リンク PEN Lite E-PL6 のキットレンズとして入手。 ・ 「 https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/14-42_35-56_2_r/index.html 」(公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/456853.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B0058G3Z5S/ 」(Amazon) | ||||||||||||||||
[TIPS] 色収差&歪曲収差補正(OM Workspace)E-PL6などの古いオリンパス製ボディは色収差補正に対応していないものの、 純正のRAW現像ソフトウェア「OM Workspace」から手動で補正できる。 以下は私が独自に検証した補正値。だいたい消えると思うが最終的には目視確認、しよう(提案)
本当のことを言えば18mmでもやや糸巻型だがかなり小さな歪みなので補正しないことにした。 | ||||||||||||||||
| OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R | ||||||||||||||||
| 【フィルター径φ58mm】 【手ブレ補正なし】 【寸法φ63.5x83mm】 【重量190g】 【インナーフォーカス】 | ||||||||||||||||
クリックして展開2011年に発売された望遠ズームレンズ。「R」と付かないモデルはデザイン変更前のもの。 非常に息の長いレンズで、発売から11年を経た2022年現在でも販売されている。 カラーバリエーションはブラックとシルバーの二色展開。専用フードはLH-60(別売)。 ■光学性能 (評価中) ■外観など (評価中) ■購入メモ、リンク リコレにて、2022,12,01購入⇒2022,12,02発送⇒2022,12,04受取。 本体2,980円+送料550円。中古品(Dランク:難あり)。フロント・リアレンズキャップ付属。 フィルター枠付近はスレがかなり多い。レンズ内には多数のチリが入っている。 後玉のコーティングは粒子状に剥がれているように見える。とにかく状態が良くない。 ・ 「 https://jp.omsystem.com/product/lens/zoom/mzuiko/40-150_40-56_r/index.html 」(公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/472108.html 」(デジカメWatch・ニュースリリース) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B0058G4066/ 」(Amazon) | ||||||||||||||||
| 単焦点レンズ | |
|---|---|
 |
左から、 ・ Meike 3.5mm F2.8 (円周魚眼レンズ) ・ Laowa 6mm F2 Zero-D MFT ・ SIGMA Art 19mm F2.8 DN (A013) |
| Meike 3.5mm F2.8 (円周魚眼レンズ) | |
| 【フィルター装着不可】 【電子接点なし】 【寸法φ60x48mm】 【重量190g】 【インナーフォーカス】 【MF専用】 | |
クリックして展開2020年に発売された円周魚眼(Circular fisheye)レンズ。 非常に小さいながらも画角は220°にも達しており、容易に撮影者自身が写り込む。 このレンズは電子接点を持たないため、フォーカシングと絞り込みは手動で行う必要がある。 ■光学性能 魚眼レンズの光学性能というのはどうやって測ればいいのだろうか・・・? 感覚的には割と優れた解像力を持っていると感じる。 ■外観など 低価格ながらも鏡筒はフルメタル製となっており質感は非常に良い。 ただ、フォーカスリングが六角ナットのようなデザインになっていて少々気に入らない。 おそらくは指先の感触で絞りリングと判別できるようにした結果だとは思うが・・・。 付属するプラスティック製のフロントキャップは非常に外れやすいので注意。 引っ掛かりが甘いらしく、少し傾いた、と思ったらそのままズルッと全部外れてしまう。 ■購入メモ、リンク Amazonにて、2024,02,25注文⇒2024,02,26発送⇒2024,02,27受取。 本体16,650円+送料無料。新品。 ・ 「 http://www.mkgrip.com/goods/show-335.html 」(公式サイト・英語) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1271652.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08CBBNJW5/ 」(Amazon) | |
| Laowa 6mm F2 Zero-D MFT | |
| 【フィルター径φ58mm】 【手ブレ補正なし】 【寸法φ61x52mm】 【重量188g】 【インナーフォーカス】 【MF専用】 | |
クリックして展開2023年に発売された広角単焦点レンズ。 このレンズの画角121.9°は同社曰く2023年2月時点で「マイクロフォーサーズ市場で最も広い画角」であるという。 マニュアルフォーカス専用レンズながら電子接点を持つため、絞り値をボディ側から制御できるほか、 EXIF情報の記録や手ブレ補正の焦点距離設定をボディが自動で行えるようになっている。 MF専用レンズとしては比較的高価なモデルであるためか、中古品の流通量は少なく感じる。 実際、手元の個体は発売から1年以上経過した時点で取り寄せしたものであるが、 シリアルナンバーはNo.001006と量産品にしては若い番号が振られている。 ■光学性能 (評価中) ピントリングは少し重めだがスムーズに回る。 個体差かもしれないが、手元の個体ではピントリングがオーバーインフまで回らないようだった。 最近のレンズ(特にAFレンズ)はオーバーインフまで回る方が一般的だと思うので少々意外。 良く言えばキッチリ調整されている証拠だが、逆に本当にインフが出ているか若干不安になる。 また、絞り羽根の動作音が少々特徴的で、「ジャリッ!ジャリッ!」という具合の音が出る。 ■外観など 高価格なだけあってフルメタル製。しかも鏡筒だけでなくフードまでメタル製となっている。 そのせいか若干フードの着脱が固いが、フードを含めてかなり堅固な印象を与えるレンズに仕上がっている。 ■購入メモ、リンク カメラのキタムラにて、2024,02,21注文⇒2024,02,23決済確認⇒2024,03,18入荷・発送⇒2024,03,19受取。 本体94,050円+送料無料。新品。 ・ 「 https://www.laowa.jp/cat1/6bc1e9b0f1db3155e59eb33514e08d6a3d07f386.html 」(公式ページ) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1476424.html 」(デジカメWatch) | |
| SIGMA Art 19mm F2.8 DN (A013) | |
| 【フィルター径φ46mm】 【手ブレ補正なし】 【寸法φ60.8x45.7mm】 【重量160g】 【インナーフォーカス】 | |
クリックして展開2013年に発売された単焦点レンズ。 ■光学性能 (評価中) ■外観など (評価中) ■購入メモ、リンク カメラのキタムラにて、2023,09,06注文⇒2023,09,09発送⇒2023,09,10受取。 本体8,250円+送料550円。中古品B。 フード、前後キャップ付属。フォーカスリングがかなりキズだらけ。 ・ 「 https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a_19_28/ 」(公式サイト) | |
■Eマウント・フルサイズ(FEマウント)
サードパーティー製レンズが数多く発売されているためレンズ選びが楽しい。
フルサイズ機は通称「FEマウント」とも呼ばれるが、マウント規格自体はEマウントそのものである。
| SONY α7R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
( 撮影 : α57 + SAL1855 ) SILKYPIX Pro11、フラッシュON |
||||||||||
クリックして展開2013年発売のフルサイズセンサー搭載ミラーレスカメラ。 先に発売されていた「NEX」シリーズよりも本格的なレンズ交換式カメラに仕上がっている。 α7Rは同時発売のα7よりも高画素機である反面、像面位相差AF非対応となっており連写速度も低い。 後継機は「α7R II」。α7RIIではグリップ回りが変更されたので、このルックスは一世代限りのものとなった。 なお、充電はNEX-6などと同じくmicroUSB端子から行える。 ヒンジも同じような造りとなっていて、開閉のストレスで千切れたりはしないと思われる。 ■オートフォーカス、動画撮影 (評価中) ■ファインダー、背面液晶 (評価中) ■シャッター音
ミラーレス機の中でもレリーズタイムラグが大きいという噂通り、 シャッターボタンを押し切ってからだいぶ遅れてシャッターが切れる。 なおこのカメラボディには電子シャッターどころか電子先幕すらないので、 先幕・後幕ともにメカシャッター固定となっている。 ■現像設定、購入メモ、リンク クリエイティブスタイルは「ニュートラル」にしている。 カメラのキタムラ(通販)にて、2024,01,30注文・店舗発送⇒2024,02,01センター発送⇒2024,02,02受取。 本体70,100円+送料550円。中古品B(並品)。元箱と取扱説明書が欠品。 液晶コーティング除去済み(?)、目立たないが背面液晶の中央に小さなムラがある。 初のショッピングローン(12回払い)活用例になった。 ・ 「 https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7R/ 」(公式サイト) ・ 「 https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201310/13-1016/ 」(公式プレスリリース) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/623578.html 」(デジカメwatch・レビュー) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/623858.html 」(デジカメwatch・インタビュー) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B00FXKLN58 」(Amazon) | |||||||||||
| 単焦点レンズ | |
|---|---|
 |
左から、 ・ Samyang AF 35mm F1.8 FE |
| Samyang AF 35mm F1.8 FE | |
| 【フィルター径φ58mm】 【手ブレ補正なし】 【寸法φ65.0x63.5mm】 【重量210g】 【インナーフォーカス】 【防塵防滴】 | |
クリックして展開2020年に発売された標準単焦点レンズ。 小型軽量かつウェザーシーリング付きと使い勝手の良い仕様であると同時に、 実勢価格で新品4万円を切る低価格(2024年2月時点)を実現している。 同社からは同じ焦点距離でF2.8のレンズとF1.4のレンズも発売されている。 すべての個体が同じかは不明だが、手元の個体は「MADE IN KOREA」であった。 Samyang社は韓国企業なので現地生産であるようだ。 ■光学性能 (評価中) 最短撮影距離29cmで最大撮像倍率0.17倍なので、小さな被写体に寄って撮ることは難しい。 ■外観など おそらくはプラスティック製。表面はザラザラとした仕上げで光沢はない。 ピントリングは軽く、スムーズに回る。「MODE」スイッチを切り替えると絞り環として機能する。 ■購入メモ、リンク Amazonにて、2024,02,28注文⇒2024,02,29発送⇒2024,03,02受取。 本体31,883円+送料無料。Amazonアウトレット(非常に良い)。 ・ 「 https://www.samyanglens.com/jp/product/product-view.php?seq=516 」(公式ページ) ・ 「 https://www.kenko-tokina.co.jp/newproducts/samyang_af35mmf18news20201106.html 」(公式ニュースリリース) ・ 「 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000990.000008859.html 」(PRTIMESプレスリリース) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1287630.html 」(デジカメWatch・発売情報) | |
| フラッシュ(ストロボ) | |
|---|---|
 |
左から、 ・ MINOLTA PROGRAM 3600HS(D) + SONY ADP-MAA |
| MINOLTA PROGRAM 3600HS(D) | |
クリックして展開ミノルタ製のオートロックアクセサリーシュー対応クリップオンストロボ。 その名の通り最大光量はガイドナンバー36で、中型ストロボに分類される。 後にSONYから発売された「HVL-F36AM」は3600HS(D)のリネーム品と言われている。 電源は単三電池4本。・・・なのだが電池蓋が非常に開けづらい。 特に電池が入った状態ではやたらと引っ掛かるのでフタを壊しそうで怖い。 ■性能 フラッシュ調光補正には対応していない。 フラッシュブラケットにもおそらく非対応。 対応する画角は24/28/35/50/85mmでオートズームが可能。 ワイドパネルを装着することでさらに広角レンズにも対応する ・・・が、中古品につき付属していなかったので未確認である。 なおハイスピードシンクロに対応している。 大光量フラッシュらしく横位置でのバウンス撮影には対応しているものの、 左右への首振りができないため縦位置でのバウンス撮影はできない。 キャッチライトパネルも搭載されていないため人物の撮影には向いていないと思われる。 また、俯角を付けられないので至近距離での撮影もやや苦手とする。 ミノルタ製品のためAマウント機ではADI調光にも対応する。 が、同等品とされるHVL-F36AMの互換性情報によると、Eマウント機に装着する場合は ADI調光とAF補助光の機能が使用できなくなる模様。 ■外観など フルプラスティック製でモニターはない。 設定はそれぞれインジケーターランプで確認することになる。 操作は押しボタン4つで行う。あまり設定項目が多くないので迷うことはないだろう。 電源OFFの操作が若干分かりづらいと思うのだが、 「ON/OFF」ボタンを押してOFFのランプが灯った状態で少し放置すると電源OFFになる。 ■購入メモ、リンク ハードオフにて、2024,02,01注文・発送⇒2024,02,03受取。 本体4,400円+送料1,100円。中古品。ワイドパネル欠品。 フラッシュポーチ、ミニスタンド、ADP-MAAが付属。 ・ 「 https://kakaku.com/item/10601710012/ 」(価格.com) ・ 「 https://www.sony.jp/ichigan/products/HVL-F36AM/ 」(HVL-F36AMの公式ページ) ・ 「 https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/flash_list.php?area=jp&lang=jp&mdl=HVL-F36AM 」(HVL-F36AMの互換性情報) | |
| SONY ADP-MAA | |
クリックして展開オートロックアクセサリーシュー対応のアクセサリーを マルチインターフェースシューに取り付けるための変換アダプター。 ■外観など フルプラスティック製。 マルチインターフェースシュー側は根元部分のネジを回転させて固定する。 固定力はそこまで悪くないと思うが場所が場所だけに操作性は悪い。 特に大型ストロボ使用時は手を入れられる空間が狭くなるため、 ADP-MAAだけを先にボディへ取り付けておくと良いかもしれない。 また、変換アダプターが間に挟まる分グラつきが大きくなるので少し気になる。 ■購入メモ、リンク 3600HS(D)とのセット品として入手。中古品。 マルチインターフェースシュー側の保護カバーが付属。 ・ 「 https://www.sony.jp/ichigan/products/ADP-MAA/ 」(公式サイト) | |
■Eマウント・APS-C
| SONY α NEX-6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
( 撮影 : EOS7D + EF-S18-55mmSTM ) SILKYPIX Pro11、フラッシュON |
||||||||||
クリックして展開2012年発売のAPS-Cサイズイメージセンサー搭載ミラーレスカメラ。 「NEX」シリーズ末期のカメラであると同時に、同シリーズで初めてモードダイヤルを搭載したモデルでもある。 NEX-5Rの上位モデルであり、NEX-7の下位モデルである。後継はα6000シリーズと思われる。 なお、NEX-6はmicro-B端子からUSBで充電する。(バッテリーパックも着脱可) そのためか専用のバッテリーチャージャーは付属せず、代わりにUSB充電器とUSBケーブルが付属している。 ちなみにUSB/HDMI端子のある部分のフタには金属製のヒンジが入ってるので耐久性に期待できる。高評価。 ■オートフォーカス、動画撮影 一応(コントラストAF併用の)像面位相差AF対応ではあるものの、対応エリアがかなり狭い。 レンズにもよるかもしれないがフォーカシングの動きも緩慢なのでアテにしないほうがいいと思う。 ちなみに、AF動作後に画面のフチに緑の破線が表示される場合は「AF補助光でAFした」という表示らしい。 画面中央付近でAFするらしいが、どこに合わせたのか表示されることはないのでどうも不安になる。 そしてなぜかこの挙動の説明がαハンドブックにしか載ってないので少々困惑した。 ■ファインダー、背面液晶 ファインダーは色割れもなく高精細で非常に良好。 ただし覗ける角度がなぜか結構シビアで、ズレた位置から覗くとズレたVRゴーグルのような見え方になる。 また、アイピースカップが比較的小さいため光源の位置によってはファインダーが少々見づらくなる。 背面液晶は十分に精細で色味も良く、特に不満はない。 が、あえて言うならヒンジがやや硬いため角度を変えにくいと感じるかもしれない。 バッテリー残量のパーセンテージ表示が一部の表示スタイルでしか現れないのも少しマイナス。 ところでこれはここに書くことではないが・・・このカメラは電源ONから撮影可能になるまでの時間が結構長い。 というか電源OFFにも結構時間がかかる。なぜこうも緩慢なのかは分からないがとにかく動きが重い。 もしシャッターチャンスの少ない撮影を行うのなら気を付けたほうが良いだろう。 ■シャッター音
・・・が、ミラーレスにしてはなかなかうるさいので注意。 ■現像設定、購入メモ、リンク クリエイティブスタイルは「スタンダード」にしている。 Amazonにて、2023,10,01注文・発送⇒2023,10,03受取。 本体24,000円+送料無料。中古品(非常に良い)。取扱説明書とアイピースカップが欠品。 16GBのSDカードを付けてもらえた・・・が中身を消し忘れている。 おそらくはマイナンバーカードの写真撮影に使われていたSDカードなのだろう。 ・ 「 https://www.sony.jp/ichigan/products/NEX-6/ 」(公式サイト) ・ 「 https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201210/12-1030/ 」(公式プレスリリース) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B009Z3PBWA/ 」(Amazon) | |||||||||||
| 単焦点レンズ | |
|---|---|
 |
左から、 ・ Carl Zeiss Touit 2.8/12 ・ SIGMA Art 30mm F2.8 DN (A013) ( 撮影 : EOS7D + EF-S18-55mmSTM )
SILKYPIX Pro11、フラッシュON |
| Carl Zeiss Touit 2.8/12 | |
| 【フィルター径φ67mm】 【手ブレ補正なし】 【寸法φ88x68mm】 【重量260g】 【インナーフォーカス】 | |
クリックして展開2013年に発売の明るい広角単焦点レンズ。 名前は「トゥイート」と読む(らしい)。ところが系統名としては「Distagon」である。 「Touit」シリーズはAPS-Cセンサー専用とすることで(比較的)リーズナブルな製品群となっているようだ。 ■光学性能 (評価中) ■外観など このお値段でまさかの金属外装採用である。非常に質感が良い。 フォーカスリングには表面に模様のないゴム製の滑り止めが施されている。回し心地は良好。 鏡筒の左右とフロントレンズキャップには青い四角に白文字で「ZEISS」と入ったロゴがあしらわれている。 ■購入メモ、リンク Amazonにて、2023,10,05注文⇒2023,10,06発送⇒2023,10,08受取。 本体41,300円+送料無料。中古品(ほぼ新品)。 ・ 「 https://www.zeiss.co.jp/consumer-products/photography/touit/touit-2812.html 」(公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/599536.html 」(デジカメWatch) | |
| SIGMA Art 30mm F2.8 DN (A013) | |
| 【フィルター径φ46mm】 【手ブレ補正なし】 【寸法φ60.8x40.5mm】 【重量140g】 【インナーフォーカス】 | |
クリックして展開2013年に発売された単焦点レンズ。 ■光学性能 (評価中) ■外観など (評価中)() ■購入メモ、リンク ハードオフ(OFFモール)にて、2023,10,02注文・発送⇒2023,10,04受取。 本体11,000円+送料1,400円。中古品(Bランク)。 フード、前後キャップ、ケース、説明書、外箱付属。 おそらく完品。 PRO1Dレンズプロテクターも付いてきた。 ・ 「 https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a_30_28/ 」(公式サイト) | |
■Aマウント
ミノルタはボディ内手ブレ補正を採用したため、レンズには手ブレ補正機能がないことが多い。
なぜか人気がないマウントであるため、同じレンズでもAマウントモデルだけ安いことがある。
最後までボディからAFカップリングが廃止されなかったため、ある意味Fマウント以上に互換性がある。
| SONY α57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
( 撮影 : α7R + EF50mmII + EF-NEX ) SILKYPIX Pro11、フラッシュON |
|||||||||||||||||||||||||||||
クリックして展開2012年発売のAPS-Cサイズイメージセンサー搭載一眼カメラ。 一般的なクイックリターンミラーの代わりに「トランスルーセントミラー」と称するハーフミラーを搭載し、 センサー露光時でもミラーの跳ね上げ動作を不要としている。そのためライブビューでも位相差AFで動作する。 スチル撮影ではセンサーシフト方式、動画撮影では電子式のボディ内手ブレ補正も使用できる。 SDカードをこのボディでフォーマットするとexFATにフォーマットされる。 FAT32ではファイルサイズの上限(4GB)があるからではないかと推測しているが真相は不明。 ■オートフォーカス、動画撮影 オートフォーカスは常に位相差AFであるため一般的な一眼レフカメラと同じく高速。 動画撮影中もコンティニュアスAFが使えるため、オートフォーカス性能はかなり優秀と言える。 また、マニュアルフォーカス時には「ピーキング」というピントの合っている部分の強調表示が使える。 この機能は便利であると同時に見てて楽しい。 動画撮影機能は1920x1080pxの60fpsにまで対応する。 ・・・が、残念なことにAF使用時は強制的にPモードで動作することになる。 そのためシャッタースピードを固定できない。 この仕様は各社の一眼レフ向けマウントレンズで見られるものだが理由は不明。 動画撮影時にシャッタースピードがフレームレートより速い場合、 撮影結果がパラパラ漫画のようになってしまい動きをスムーズに表現できなくなってしまう。 そのため、特に明るい場所で動画撮影を行うとあまり良い結果にはならないだろう。 やはりレフ機はミラーレスに及ばないのだろうか・・・。 なお、MFであればP/A/S/Mモードすべてが使えるためシャッタースピードを固定できる。 ピーキング機能は動画撮影中でも機能するため、同種の機能がないカメラよりは合わせやすい。 ■ファインダー、背面液晶 搭載するファインダーはAマウント機ながらEVFとなっている。解像度は144万画素。 DMC-GH1よりはだいぶマシなものの、このEVFもまたフィールドシーケンシャルカラー方式らしく色割れが生じる。 また、色味が ・ 『 フィールド・シーケンシャル・カラー表示における色割れと視者視力および色表示周波数の関係 』 一方、背面液晶パネルは92万画素とそこそこ精細で色味も良い。 液晶面を内に向けることでキズ・ヨゴレを防止できる点はDMC-GH1と同じ。 ファインダー、背面液晶とも二軸の電子水準器の表示に対応している。 これがなかなか見やすくできていて、大型ながらも前方の視界は良好で非常に便利である。 ■シャッター音
ミラーの跳ね上げがないため普通の一眼レフとは違う・・・とはいえ何とも言えない不思議な音である。 ■現像設定、購入メモ、リンク クリエイティブスタイルは「スタンダード」にしている。 自室で撮影する際はISO800、F5.6、SS1/15にしている。 リコレにて、2022,12,09注文⇒2022,12,10発送⇒2022,12,13受取。 本体19,980円+送料550円。中古品Aランク。 取扱説明書、CD-ROM、ストラップ、ケーブル、ボディキャップ、充電器が付属。 ・ 「 https://www.sony.jp/ichigan/products/SLT-A57/index.html 」(公式サイト) ・ 「 https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201203/12-0321/ 」(公式プレスリリース) ・ 「 https://ascii.jp/elem/000/000/684/684369/ 」(ASCII.jp) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B007S6Q0QM/ 」(Amazon) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[TIPS] PCでのRAW現像に関して (Image Data Converter)α57には専用のRAW現像ソフトとして 「 Image Data Converter 」(IDC) が用意されていた。 現在は 「 Imaging Edge Desktop 」 が案内されているが、とりあえずIDCの方を使ってみようと思い、 InternetArchiveからソフトウェアのexeファイルを入手した。 ・ 「 https://web.archive.org/web/20180114071152/http://www.sony.jp/support/software/idc/download/ 」 ちなみに、公式サイトはダウンロードリンクを消しただけでファイル自体はまだ残っているらしく、 オリジナルのURLを入力するとフツーにダウンロードできた。(2022,12,14時点) ( ttp://support.d-imaging.sony.co.jp/download/IDC/hfU4ZAqQVv/IDC510_1705a.exe?fm=jp ) IDCはクリエイティブスタイルやホワイトバランスを継承してくれるものの、 ボディ現像と仕上がりが違っており、色合いはわずかに緑っぽく、そしてソフトな風合いになる。 色合いはともかく解像感があまりにソフトで気になるため、現像設定を少し触ることにした。 現在のところは以下の設定で現像している。( 書いていない部分は標準のまま )
ボディ現像でも少しソフトすぎる感じがあったので思い切ってカチカチに硬質な画になるようにした。 そのためボディ現像に比べてノイズ耐性が低くなっている点に注意が必要。 ・・・とはいえボディ現像のISO3200なんかを見ると結構無理してノイズを消してる感じがあったので、 画をホヤホヤにしてノイズを消すよりノイジーでもカチッとさせるには上の設定くらいで良いだろう。 ちょうどEOS7Dあたりはそんな感じの画作りだと思う。(私はその方が好きなのだ) ノイズリダクションが「切」の場合にシャープネスをキツくすると偽輪郭が生じてしまい、 かなり不自然になってしまうため、ISO100ではシャープネスの値がすべて標準設定のままになっている。 色調の調整は緑っぽさを取るためのもの。(マニュアルWB時のみで良いと思う) なお、メニューバーにある 編集>画像処理設定>読み込み(適用) で処理設定を読み込んだ場合、 レンズ補正の倍率色収差補正が効かなくなるため、補正する場合は数値を手入力する必要がある。 なぜ設定項目ごとに保存できないのだろうか・・・。 ■リンク ・ 「 https://www.sony.jp/support/software/idc/ 」 (公式サイト) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インナーフォーカス
 
( 撮影 : α57 + TAMRON17-50mm ) 色温度6000K 色補正+10 |
|
||||||||||||||||||
【歪曲収差検証】
広角端ではタル型・・・に見える陣笠型収差、ズームするほど改善する。 望遠端では画面端での歪曲収差がほぼなくなるが、中央付近は糸巻型収差が残っている。 ・ 「 (独立記事作成予定) 」 | |||||||||||||||||||
クリックして展開2010年に発売された広角ズームレンズ。世界で初めて8mmをカバーした広角ズームレンズであるという。 FLDガラスを4枚、SLDガラスを1枚採用した豪華なレンズ構成により、解像力と価格を上昇させている。 フードは内蔵式で外筒に固定されている。ズームすると内筒(レンズ前群)が後退するがケラレは出ない。 アダプターリングはフードのようにも見えるが16mmでもケラレが出る、事実上のかぶせ式キャップ。 ■光学性能 (評価中) ■外観など (評価中) ■購入メモ、リンク ハードオフ(OFFモール)にて、2023,01,01注文⇒2022,01,01発送⇒2022,01,03受取。 本体30,800円+送料1,500円。中古品(Bランク)。 アダプターリング、フード、前後キャップ、ケース、説明書、外箱付属。 ピントリングのゴムが白くなっている。 ・ 「 https://www.sigma-global.com/jp/lenses/8_16_45_56/ 」(公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/366133.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=1050/id=10917/ 」(価格.com 新製品ニュース) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B003G22FFW/ 」(Amazon) | |||||||||||||||||||
[TIPS] 歪曲収差補正・簡便法(GIMP2.8)SONY謹製ソフトウェアのImageDataConverterでは、 TAMRON製を含むSONY製でないレンズで撮影したRAWデータは収差を補正してくれない。 そこで、これらのレンズで撮影した分はGIMPを使ってJPEG/TIFFのファイルから収差補正を行うことにしている。 EFマウントのTAMRON17-50mm(B005E)のように完全に補正することを目標とすると、 補正値を探るのがかなり面倒であったため、今回は「おおむね」補正できる値を探した。 こちらのほうが中途半端な焦点距離で撮影した場合でも補正値を割り出しやすいという利点もある。 なお、「Fix-CA」プラグインによる色収差補正は検証していない。 ・ Fix-CA ・・・ 「 https://kcd.sourceforge.net/fix-ca.php 」 以下は私が独自に調べた補正値。
特に8-12mmの場合は陣笠型の歪みの影響で、周辺部が少しタル型に、中央付近が少し糸巻型になる。 14-16mmも少し陣笠型に歪むが、補正が必要なほどではないので「必要なし」としている。 ・ 「 (独立記事作成予定) 」 | |||||||||||||||||||
| TAMRON SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] (A16S) | |||||||||||||||||||
インナーフォーカス
 
( 撮影 : EOS7D + SIGMA18-50mm ) |
|
||||||||||||||||||
【解像力検証】 16MP
開放絞りでも水平解像度の1/2程度までなら十分写る。 F5.6では大部分がよく写るようになる。大口径標準ズームとしては良い印象。 ・ 「 TAMRON SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD (A16S) 【解像力検証16MP】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||||||||||||
【歪曲収差検証】
広角端ではタル型・・・に見える陣笠型収差、35mm辺りが最も歪みが少ない。 望遠端では少し糸巻型収差が出ている。 ・ 「 (独立記事作成予定) 」 | |||||||||||||||||||
クリックして展開2006年に発売された大口径標準ズームレンズ。 「SP」を冠する高品質なレンズで、光学性能では後継モデルのB005よりも高いものを持っている。 専用フードは花形フードの「DA09」。 ■光学性能 解像力検証の結果の通り、開放絞りでも日の丸構図なら十分に写せる。 倍率色収差がそれなりにあるため、できればRAW現像時に補正しておきたいところ。 お値段も割安感があるので、手軽に動く被写体を撮りたい人には良い選択肢になると思う。 AF時にはボディ内モーターを使用して駆動する。 TAMRON18-250mm(A18)よりもフォーカシングに使うレンズが軽いのか、動作が速いように感じる。 ただしかなりうるさい。 ■外観など 外装はプラスティック製。意匠はこの時期のTAMRONによく見られるもの。(好み) 個体差かもしれないが、ズームリングに少し遊びがあり、望遠端方向に力がかかった状態では 以下のような不具合を生じるようだった。 ・ 35mmの指標に合わせたはずなのにEXIFに40mmと記録される、 ・ 50mmに合わせているとAFがサーチ駆動し続けてしまい合焦しない ■購入メモ、リンク Amazonにて、2023,01,01注文⇒2022,01,01発送⇒2022,01,03受取。 本体10,190円+送料無料。中古品(非常に良い)。たぶん完品。 ・ 「 https://www.tamron.co.jp/lineup/a16/index.html 」(公式サイト) ・ 「 https://www.tamron.co.jp/news/release_2006/news1115_a16.html 」(公式ニュースリリース) | |||||||||||||||||||
[TIPS] 歪曲収差補正・簡便法(GIMP2.8)SONY謹製ソフトウェアのImageDataConverterでは、 TAMRON製を含むSONY製でないレンズで撮影したRAWデータは収差を補正してくれない。 そこで、これらのレンズで撮影した分はGIMPを使ってJPEG/TIFFのファイルから収差補正を行うことにしている。 EFマウントのTAMRON17-50mm(B005E)のように完全に補正することを目標とすると、 補正値を探るのがかなり面倒であったため、今回は「おおむね」補正できる値を探した。 こちらのほうが中途半端な焦点距離で撮影した場合でも補正値を割り出しやすいという利点もある。 なお、「Fix-CA」プラグインによる色収差補正は検証していない。 ・ Fix-CA ・・・ 「 https://kcd.sourceforge.net/fix-ca.php 」 以下は私が独自に調べた補正値。
特に24mmより広角な場合は陣笠型の歪みの影響で、中央付近が少しタル型になる。 35-50mmは少し糸巻型に歪むが、補正が必要なほどではないので「必要なし」としている。 ・ 「 (独立記事作成予定) 」 | |||||||||||||||||||
| SONY DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL1855) | |||||||||||||||||||
前玉回転式
 
( 撮影 : DMC-GH1 + Panasonic12-32 ) |
|
||||||||||||||||||
【歪曲収差検証】
広角端ではタル型収差、望遠端ではほぼ歪曲収差なし。ズームするほど改善する。 α57のボディ内補正でおおむね補正できるが、18mmではごくわずかに糸巻型になっている。 ・ 「 (独立記事作成予定) 」 | |||||||||||||||||||
クリックして展開2009年に発売された標準ズームレンズ。 2012年にはマイナーチェンジモデルの「SAL1855B」が発売されている。後継モデルは「SAL1855II」。 専用フードは円形フードの「ALC-SH108」。 ■光学性能 AF時には内蔵モーターである「スムーズAFモーター」(SAM)で駆動する。 ボディ内モーターに比べてその名の通りスムーズに駆動するというが、あくまでも普通のDCモーター。 さすがに超音波モーターやステッピングモーターには速度でも静穏性でも敵わない。 MF時はあまりにも小さなピントリングのせいで操作性が少々悪い。 が、前玉回転式のためレンズフード装着時はレンズフードを掴んで回すことができ、意外と快適。 ■外観など 外装はプラスティック製。意匠は好みにもよると思うがあまり・・・うん。 ズームリングの近くにネジが露出しているのはちょっとマイナスだと思う。 そして専用レンズフードは広角27mm相当にしてもあまりに短い。 ズームリングは40mmあたりのところがやけに渋い・・・がこれは仕様らしい。 ・ 「 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000035099/SortID=19872252/ 」 ■購入メモ、リンク Amazonにて、2022,12,09注文⇒2022,12,11発送⇒2022,12,13受取。 本体5,000円+送料無料。中古品(非常に良い)。完品(キタムラの保証書付き)。 ピントリングが白くなっていたが、アルコールティッシュで拭ったところだいたいキレイになった。 ・ 「 https://www.sony.jp/ichigan/products/SAL1855/index.html 」(公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/531733.html 」(デジカメWatch、SAL1855B) ・ 「 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000035099/SortID=14415206/ 」(価格.com、SAL1855B) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B002AROQJW/ 」(Amazon) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B007AAT7BQ/ 」(Amazon、SAL1855B) | |||||||||||||||||||
| TAMRON AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] MACRO (A18S) | |||||||||||||||||||
インナーフォーカス
 
( 撮影 : α57 + SAL1855 ) |
|
||||||||||||||||||
クリックして展開2007年に発売された高倍率ズームレンズ。 専用フードは花形フードの「DA18」。 ■光学性能 AF時にはボディ内モーターで駆動する。 ・・・が、これがかなりうるさい。動きもあまり速いとは感じられない。 AF/MFはボディ側のスイッチで切り替える。(レンズにスイッチはない) MF時もギアがかみ合ったままになっているのかピントリングが重い。 ■外観など (評価中) ■購入メモ、リンク リコレにて、2022,12,24注文⇒2022,12,26発送⇒2022,12,29受取。 本体4,880円+送料550円。中古品(Cランク)。外箱、フード、フロント・リアレンズキャップ付属。 ピントリングが白くなっている。アルコールティッシュで拭ったが良くならなかった。 ・ 「 https://www.tamron.co.jp/data/af-lens/a18.html 」(公式サイト) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B000N8F680/ 」(Amazon) | |||||||||||||||||||
| MINOLTA AF REFLEX 500mm F8 | |||||||||||||||||||
前玉回転式
 
( 撮影 : α57 + SAL1855 ) |
|
||||||||||||||||||
【解像力検証】 APS-C 16MP
画面全体でよく写る。ハッキリ言ってスゴいレンズ。 ・ 「 MINOLTA AF REFLEX 500mm F8 【解像力検証APS-C・16MP】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||||||||||||
クリックして展開かつてミノルタが販売していたミラーレンズ(レフレックスレンズ)。 F6.7-F8の光束が通るように副鏡を小型化し、AF動作を実現している模様。 (※SAL500F80の説明より) 反射光学系を採用したことにより、全長118mm・重量665gで500mmの超望遠撮影を実現している。 専用の円形フードはねじ込み式。フィルターは専用品(Normal/ND4x)を後部に差し込んで使用する。 ■光学性能 解像力検証の結果を見てわかる通り写りはかなり優秀。色収差もほぼゼロ。 屈折光学系の安い望遠ズームレンズではまず達成できないであろう撮影結果をもたらす。 ただし、絞りがF8固定であるため三脚がなければ明るい環境でしか使えず、 倍率は500mm固定であるためフレーミングも難しい。使いどころを見極めよう。 AF動作はボディ内モーターで行うが、意外とスピードはそこまで遅くもない。 が、さすがに回転する部分が重いのかカメラが軽く回転方向に揺さぶられる。 なお、このレンズを装着している場合は中央のAF枠しか選択できなくなるため注意。 当然追尾AFも使用できない。MF専用よりマシとはいえ屈折光学系のようにはいかないようだ。 技術的には中央AF枠の真上と真下なら横向きのラインセンサー、真横なら縦向きのラインセンサーで AF動作させることも可能ではないかと思うが・・・。 マニュアルフォーカスではピントリングを操作する・・・が、見た目ではどこがピントリングなのか分かりにくい。 正解はレンズ先端のラバー加工されている部分で、溝はないが素手なら割と快適に回せる。 回転距離が1/3周くらいあり、レンズの直径も大きいため正確にピントを合わせることが可能。 ■外観など 外装はプラスティック製。デザインは超シンプルで少々物足りなさも感じる。 筐体下側にある溝の入った部分はピントリングのようにも見えるが、これはただのグリップ。 レンズ後部にはフィルター取り付け部があり、ノブを押しながら回転させることでロックを操作できる。 手元の個体は残念ながらこの部分が壊れているため実際に操作することはできなかったが、 破損した部品を見る限り、プラスティック製ノブ、コイルスプリング、スプリングピン、の 3パーツでノブを構成しているようだ。 ■購入メモ、リンク ヤフオクにて、2023,01,01落札⇒2023,01,02発送⇒2023,01,04受取。 本体17,050円+送料1,305円。中古品。おそらく完品。 フィルターロックノブ破損。 専用ケースは外面にカビ痕(?)、底部スポンジ劣化。 ・ 「 https://web.archive.org/web/20000606170015/http://www.minolta.co.jp/japan/f_camera.html 」(公式サイト、InternetArchiveのキャッシュ版) ・ 「 https://web.archive.org/web/20001017221206/http://www.minolta.co.jp/japan/pdf/alphaspec.pdf 」(公式サイト(比較表PDF)、InternetArchiveのキャッシュ版) | |||||||||||||||||||
■EF/EF-Sマウント・APS-C
( EF-SマウントでないAPS-C専用レンズはフルサイズ機にも取り付けられるがケラレを生じる )
APS-C専用レンズはフルサイズ対応レンズに比べて安価だったり小型軽量だったりするほか、
ズームレンズではAPS-C機で使いやすいズーム域に設定されている。
| Canon EOS 10D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
|
||||||||||
クリックして展開2003年発売のAPS-Cサイズイメージセンサー搭載一眼レフカメラ。 動画撮影機能やライブビュー機能が搭載されていない、古典的なスチルカメラ。 多少不便な分だけ中古品が安く手に入る。とってもお買い得な一台。(20D/30D/40Dも安いので要検討) 画素数がもう少し欲しいところだが、APS-Cサイズの威力は十分に感じられる。 普段はISO200で使用しているがISO400でも大きな問題はない。ISO800からは暗部がキケン。 逆にISO100は使わなくていいと感じる。そうするよりはもう一段絞ったほうが画質は向上するだろう。 記憶媒体のコンパクトフラッシュは32GB(FAT32)でも認識するようだった。(FW1.0.0) 32GBあれば999枚以上撮れる(カンストする)ようなのでまず困らないだろう。 ただし、撮影データをコンパクトフラッシュからPCへ移すなどした場合、 管理ファイルの更新に時間がかかるのか、カメラの起動時間が伸びる模様。 TAMRON・18-270mmとは相性が悪いのか、あるいはAF性能の限界からなのか、前ピンになってしまう。 SIGMA・18-50mmでもピントが怪しいと感じる部分があったため、EOS7Dへ乗り換えた。 現在は予備ボディとして保管中。 ■現像設定、購入メモ、リンク ピクチャースタイルは非搭載。DPP現像時は忠実設定にシャープネス+3、色合い+1としている。 ISO感度は200/400で常用。高速シャッター用にはISO800。屋外ではISO200。 自室で撮影する際はISO200、F5.6、SS1/4にしていた。(シャッタースピードがリスキーだが・・・) カメラのキタムラにて、2022,08,19注文・店舗発送⇒2022,08,22センター発送⇒2022,08,23受取。 本体5,100円+送料550円。中古品B(並品)。ネックストラップ、バッテリーx2、充電器が付属。 付属のネックストラップにはRC-1リモコンが付いていたが、このボディでは使えない。 また、バッテリーはBP-511A、充電器はCG-580だった。純正だけど標準添付じゃない、奇妙なセット。 ・ 「 https://global.canon/ja/c-museum/product/dslr783.html 」 (公式サイト) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B00008RKYF/ 」(Amazon) | |||||||||||
Canon R-F-3 (ボディキャップ)
EFマウントに取り付けることができるボディキャップ。ただのプラスティックの円盤。 別になくても養生テープで保護するなりレンズを付けっぱなしにするなりで対応できるが、 持ち運ぶ機会の多い人にはあったほうがいいかもしれない。 ■リンク ・ 「 https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/2428a001.html 」(公式サイト) ヤフオクにて、2022,08,26落札。 本体480円+送料無料。新品。(⇒EOS10D) | |||||||||||
| Canon EOS 7D | |||||||||||
 |
|
||||||||||
クリックして展開2009年発売のAPS-Cサイズイメージセンサー搭載一眼レフカメラ。 動画撮影機能やライブビュー機能を搭載し、近代的な一眼レフの特徴を備えている。 解像度やAF性能も着実な進歩を遂げており、2022年現在でも十分な性能を発揮する。 防塵・防滴に配慮した設計により信頼性も向上しているという。 ■オートフォーカス、動画撮影 ライブビュー撮影時に使用できるコントラストAFは位相差AFに比べて、 速度で大きく劣る反面精度は高く、ほとんどの場面で正確にピントを合わせてくれる。 ただしAF枠が大きいため必要に応じて拡大する必要がある。 AF-ONボタンの隣にあるAEロックボタンにAF-OFFを割り当てておくと、 拡大してAF⇒拡大を解除して構図確認、と便利に使える。 動画撮影機能は一応付いてはいるものの、正直言って使い物にならない。 コントラストAFは合焦まで時間がかかるうえ、コンティニュアスAFもできないことから、 被写体までの距離が変わるような撮影ではまず使えない。定点観測用がいいところだろう。 ■ファインダー、背面液晶 EOS7Dのフォーカシングスクリーンには透過型液晶(※EVFではない)が搭載されているため、 ファインダー内で有効なAF枠だけを表示させられるほか、グリッド線のON/OFF切り替えもできて非常に便利。 M-Fnボタンなどにファインダー内表示の水準器を割り当てることができ、 表示中はAF枠を用いてピッチ方向とロール方向の傾きを表示してくれる。 ただし、この水準器はシャッターボタンを半押しすると消えてしまう。 背面液晶は92万画素となかなか精細で色味も良いと感じる。 角度を変えられない点が少々残念なものの、ライブビュー撮影も快適に行える。 ところが、ライブビュー中の電子水準器はまさかの画面ど真ん中に表示されるという恐ろしい仕様となっている。 水準器のデザインもアナログ式の水準器を思わせるもので、視界の真ん中をぶち抜いてくれる。 さすがにもう少し何かあっただろう・・・と思ってしまう。 ■シャッター音
■現像設定、購入メモ、リンク ピクチャースタイルは忠実設定にシャープネス+3としている。 ISO感度は800で常用。ISO1600からはノイズが増える。 自室で撮影する際はISO800、F5.6、SS1/15にしている。 リコレにて、2022,09,22注文⇒2022,09,23発送⇒2022,09,25受取。 本体26,980円+送料550円。中古品B。箱のみ欠品。 ・ 「 https://global.canon/ja/c-museum/product/dslr802.html 」 (公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/322840.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B002NEFL64 」(Amazon) | |||||||||||
| SIGMA SD1 Merrill EFマウント改造型 | |||||||||||
 |
( 撮影 : α7R + EF50mmII + EF-NEX ) SILKYPIX Pro11、フラッシュON |
||||||||||
クリックして展開2012年発売のAPS-Cサイズイメージセンサー搭載一眼レフカメラ・・・を改造したもの。 自分で改造したものではなく、中古で入手した改造品であるため詳細は不明。 SAマウントをEFマウントに改造すること自体はSD14などでも行われていたようだ。 SD1Mは前年に発売された(「Merrill」の付かない)SD1の価格改定版であり中身は同じ。 外見上の違いは背面液晶右下に「Merrill」の文字があるかないかであるという。 この”価格改定”はとてつもない値下げ幅を誇る。 SD1Mには1画素ごとに三原色(RGB)すべてのデータを取得することができるFoveonセンサーが搭載されており、 一般的なべイヤー配列センサーと異なりデモザイク処理が不要で、偽色も生じないとされている。 後継機種は「クアトロセンサー」と呼ばれるB4:G1:R1の非対称な画素構成のセンサーを採用している。 また、「fp」や「fp L」は通常のべイヤー配列センサーとなっている。 どういうわけかSD1Mにはイメージセンサーの周辺部が緑がかって写るという特性があり、 SIGMA製レンズの中でもこの現象の補正に対応したものでなければかなり不自然な撮影結果になる。 当然ながらEFマウント改造型であるこの個体にEFレンズを取り付けても緑に染まってしまう。 一方、EFマウントモデルであっても補正対応のSIGMA製レンズであれば緑に染まることはない。 なおこのカメラのRAWファイルはSILKYPIX Pro11では現像できない。注意されたし。 ■オートフォーカス、動画撮影 動画撮影機能は搭載されていない。 ■ファインダー、背面液晶 不具合によりファインダーが正常に機能していない。 ファインダーでジャスピンに合わせると撮影結果がピンボケする。 AFでは正常に合焦するためミラーは無事と思われる。 おそらくはファインダーマットが傾いて装着されているか、 ファインダーの光学系が正常に組付けられていないものと思われる。 また、ファインダーは(見た目から察しはつきそうだが)あまり覗きやすくはない。 そしてこのカメラには電子水準器もないのでカメラの傾きに気が付きにくいと感じる。 ライブビュー機能がないため、背面液晶はメニュー画面や各種設定、 そして撮影結果のプレビューに使用される。しかしあまり品質が良いとは感じない。 液晶のせいかどうかは分からないが、プレビューを拡大する際に色割れを感じる。 ■シャッター音 (評価中) ■現像設定、購入メモ、リンク カラーモードは「ニュートラル」にしている。 ヤフオクにて、2023,12,03落札⇒2023,12,04発送⇒2023,12,06受取。 本体105,010円+送料1,210円。中古品。バッテリーグリップPG-31、バッテリー2つ、充電器が付属。 商品説明にはなかったのだが、おそらくファインダーマットかファインダーの光学系に不具合がある。 ・ 「 https://www.sigma-global.com/jp/cameras/sd1-merrill/ 」(公式サイト) ・ 「 」(公式プレスリリース) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/525438.html 」(デジカメwatch) ・ 「 」(Amazon) | |||||||||||
| 広角ズームレンズ | |
|---|---|
 |
左から、 ・ SIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM ( 撮影 : EOS7D + EF24mm F2.8(初代) )
SILKYPIX Pro11、フラッシュON |
| SIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM | |
| 【フィルター装着不可】 【手ブレ補正なし】 【寸法φ75x105.7mm】 【重量555g】 【インナーフォーカス】 | |
クリックして展開2010年に発売された広角ズームレンズ。世界で初めて8mmをカバーした広角ズームレンズであるという。 FLDガラスを4枚、SLDガラスを1枚採用した豪華なレンズ構成により、解像力と価格を上昇させている。 フードは内蔵式で外筒に固定されている。ズームすると内筒(レンズ前群)が後退するがケラレは出ない。 アダプターリングはフードのようにも見えるが16mmでもケラレが出る、事実上のかぶせ式キャップ。 ■光学性能 Aマウント版の同モデルの項目に詳しい。 ■外観など Aマウント版の同モデルの項目に詳しい。 ■購入メモ、リンク Amazonにて、2023,12,08注文・発送⇒2023,12,11受取。 本体28,000円+送料無料。中古品(非常に良い)。 外箱欠品。 ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B003G20AAE/ 」(Amazon) | |
| 標準ズームレンズ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
左から、 ・ TAMRON SP AF17-50mm F/2.8 (B005E) ・ SIGMA 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM ・ Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ( 撮影 : EOS7D + EF24mm F2.8(初代) )
SILKYPIX Pro11、フラッシュON | ||||||||||||||||||
| TAMRON SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] (B005E) | |||||||||||||||||||
| 【フィルター径φ72mm】 【手ブレ補正あり】 【寸法φ79.6x94.5mm】 【重量570g】 【インナーフォーカス】 | |||||||||||||||||||
【解像力検証】 18MP
開放絞りではどの焦点距離でもよろしくない。 F5.6にまで絞ればそれほど悪くもない写りになる。 ・ 「 TAMRON SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC (B005E) 【解像力検証18MP】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||||||||||||
【歪曲収差検証】
広角端で最大のタル型収差、望遠端では歪曲収差が最小になる。 ・ 「 TAMRON SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC (B005E) 【お手軽!!歪曲収差検証】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||||||||||||
クリックして展開2009年に発売された標準ズームレンズ。手ブレ補正機能を搭載している。 F値は17-50mmで常にF2.8と明るい。 SIGMAからも全く同じ焦点距離・F値のレンズが発売されているが、あちらは1.5倍ほどの中古品相場となっている。 ■光学性能 開放絞りでは中心部はともかく、周辺部の解像力はかなり低下する。写りが重要な場合はF5.6以上が良い。 SIGMA・18-50mmで気になっていた色収差はかなり改善され、周辺部も(少し絞れば)キレイに写る。 明るく使いやすい標準ズームレンズ。(まあちょっと重いけど・・・) 現在はより解像力が高く、デジタル補正にも対応しているEF-S18-55mmSTMを入手したため稼働率が低下している。 ・・・と思っていたのだが、実際に解像力を検証したところ開放絞りの写りが想像以上に悪かった。 正直これならEF-S18-55mmSTMで開放絞り+ISO感度引き上げ、としたほうがマシである。 よって YOU ARE FIRED !!! ■購入メモ、リンク カメラのキタムラにて、2022,09,29注文⇒2022,09,29店舗発送⇒2022,10,01センター発送⇒2022,10,03受取。 本体17,100円+送料550円。中古品ABランク。箱、取扱説明書、フード、フロント・リアレンズキャップ付属。 購入時より前玉に3本のスレ傷が入っていた。キタムラの説明にはなかったのだが・・・。 ・ 「 https://www.tamron.co.jp/data/af-lens/b005/ 」(公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/332466.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/date_lens/315883.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B002OED6ZQ/ 」(Amazon) | |||||||||||||||||||
[TIPS] 色収差&歪曲収差補正(GIMP2.8)Canon謹製ソフトウェアのDigitalPhotoProfessional(ver.4.16.11.0)では、 TAMRON製を含むCanon製でないレンズで撮影したRAWデータは手動でも収差を補正できない。 そこで、これらのレンズで撮影した分はGIMPを使ってJPEG/TIFFのファイルから収差補正を行うことにしている。 手順は以下の通り。 ① 「Fix-CA」プラグインで色収差を補正する ② 「レンズ補正」フィルターで歪曲収差を補正する 以下は私が独自に調べた補正値。
なお、レンズ補正は解像度と(おそらく)関係ないものの、Fix-CAは解像度によって数値を調整する必要がある。 表の数値は解像度5184x3456pxの撮影結果に対するものである。 また、色収差の目立たない撮影結果に対してFix-CAを適用すると、かえって色ずれすることがあるので注意。 レンズ補正からお察しの通り、このレンズはおおむねタル型だが細かく見れば陣笠型に歪んでいる。 「中央部」と「周辺部」のバランスを取りながら数値を決定する必要があるため非常に面倒だった。 ・ 「 GIMP2.8で色収差&歪曲収差を補正しよう! - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||||||||||||
| SIGMA 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM | |||||||||||||||||||
| 【フィルター径φ67mm】 【手ブレ補正あり】 【寸法φ74x88.6mm】 【重量395g】 【インナーフォーカス】 【インナーズーム】 | |||||||||||||||||||
【解像力検証】 18MP
18mmでは開放でも画面端以外は良く写る。 ズームするにつれて開放での写りが悪化するが、F5.6ではズームしても悪くない写りになる。 ・ 「 SIGMA 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM 【解像力検証18MP】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||||||||||||
【歪曲収差検証】
18mmではタル型、24mmからは糸巻型。 ・ 「 SIGMA 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM 【お手軽!!歪曲収差検証】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||||||||||||
クリックして展開2009年発売の手ブレ補正機能付き標準ズームレンズ。 広角18mmに手ブレ補正搭載と屋内撮影では非常に使い勝手が良い。 お安い割にインナーフォーカス・インナーズームとシャレた設計になっている。 なぜかEFマウントモデルだけ微妙にレア(?) ■光学性能 撮れ具合については(値段を考えれば)十分優秀だろうと感じる。 ・・・が、屋外で撮影すると周辺部の解像力や、広角での倍率色収差が少し気になるかもしれない。 ズームレンズだから多少は仕方がないし、値段を考えれば・・・ね? 事実上の上位モデルに17-50mm/17-70mmが存在するが、もちろんお値段もグレードアップする。 搭載しているOS(手ブレ補正)はEF28-135mmのISよりも強いと感じられる。 18-50mm(35mm換算29-80mm)と短めの焦点距離だが十分に効果を体感できる。 そして動作音はほとんどしない。なかなか優秀である。 ただし手ブレ補正の電源が切れると「ガタンッ」と壊れたような音がして心臓に悪い。 ■外観など 外装は大部分がプラスティックで作られているため頼りないほか、 フードは外側までセラミックのようにザラザラした表面仕上げとなっており少々手触りが悪い。 なお、見た目が似ていてより高倍率ズームのモデル(18-125mm/18-250mm)も存在する。 これらはレンズ構成も重さもF値も値段も違う。流通量は18-125mmが一番多いと感じる。 ■購入メモ、参考リンク 2ndstreetにて、2022,08,25注文⇒2022,08,26発送⇒2022,08,28受取。 本体8,690円+送料770円。中古品Aランク。フロントレンズキャップ、フード付属。(S/N10927140) ヤフオクにて、2022,09,11落札⇒2022,09,12発送⇒2022,09,14受取。 本体5,000円+送料1,305円。中古品。フロント・リアレンズキャップ、フード付属。(S/N10035226) ・ 「 https://www.sigma-global.com/jp/lenses/18_50_28_45/ 」 (公式サイト) ・ 「 https://digicame-info.com/2010/03/-18-50mm-f28-45-os.html 」(デジカメInfo) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/300746.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B002330FJ8/ 」 (Amazon) | |||||||||||||||||||
| Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM | |||||||||||||||||||
| 【フィルター径φ58mm】 【手ブレ補正あり】 【寸法φ69x75.2mm】 【重量205g】 【インナーフォーカス】 | |||||||||||||||||||
【解像力検証】 18MP
18mmでは画面端とその周辺、24mmでは画面端のみの解像力が低い。 35mmと55mmでは少し絞ることで画面全体が非常に良く写る。 ・ 「 Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 【解像力検証18MP】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||||||||||||
【歪曲収差検証】
広角端ではタル型収差、望遠端ではほぼ歪曲収差なし。ズームするほど改善する。 DLOで完全に補正できる。 ・ 「 Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 【お手軽!!歪曲収差検証】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||||||||||||
クリックして展開2013年発売の手ブレ補正機能付き標準ズームレンズ。 入手した個体はおそらく EOS Kiss のキットレンズであろうホワイトモデル。ややレア。 専用フードは花形フードのEW-63C。レンズは白だが付属のフードは黒だった。 後継モデルは寸法もレンズ構成も進化した 「 F4-5.6 IS STM 」 。 ■光学性能 「 キットレンズにコレ付けちゃいかんでしょ・・・ 」 と思うくらいによく出来ている。 開放でもかなりの解像力を発揮し、ズーム域のどこであっても画面端まで満足のいく画質を提供してくれる。 オートフォーカスもステッピングモーター(STM)採用のおかげで驚くほどに静か。しかも速い。 手ブレ補正も強力で、シャッターボタンを半押しすれば静かにブレを止めてくれる。 欠点はやはりF3.5-5.6と暗いところだが、それさえ受け入れられるなら非常に良い選択肢と思う。 ( とはいえ現在はF4-5.6があるので理由がないならアチラを選ぶことになるだろう ) ピントリングはバイワイヤ方式であるため通電中にしか機能しない。 かなり軽い力で回り、クリック感も動作音もないのでそもそも反応しているのか分かりにくい。 オートフォーカス時はもちろん回転しない。 鏡筒はズームリングが30mm程度の位置に来ると最も短くなり、望遠端でも広角端でも伸びる。 このことからおそらくは2群ズームの系譜にあるものと思われる。( だから軽いのか・・・? ) ちなみに後継のF4-5.6は3群ズームに変身したのか広角端で最短となる模様。 ■外観など 外装は少しざらつきのあるプラスティック製で、色が白ということもあり高級感はない。 さらにはマウントまでプラスティック製なので、正直質感はだいぶ安っぽい感じがする。 ピントリング、ズームリング、スイッチの各パーツはやや灰色気味でツートンカラーとなっている。 マイナス点として、ISやAFのスイッチがあまりに薄型であるため非常に押しづらい点が挙げられる。 それほど頻繁に操作することはないとはいえ、手袋等をしている状態ではまず押せないだろう。 ところでなんだかリアキャップが緩い気がするが、これは個体差なのだろうか・・・? ■購入メモ、リンク カメラのキタムラにて、2022,11,01注文・センター発送⇒2022,11,02受取。 本体7,300円+送料550円。中古品Bランク。フロント・リアレンズキャップ、フード、説明書付属。 ・ 「 https://global.canon/ja/c-museum/product/ef427.html 」 (公式サイト) ・ 「 https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/72948/~/【交換レンズ】ef-s18-55mm-f3.5-5.6-is-stm-機種仕様/ 」 (公式サイト・MTFあり) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B00BXVR97M/ 」 (Amazon) | |||||||||||||||||||
JJC LH-63C ホワイト
Canon・EW-63Cとの互換性を有する花形フード。 シルエットは純正品とほぼ同じだがホワイトモデルがラインナップされている。 ただし、このホワイトはややクリームがかっており、EF-S18-55mmSTMのホワイトとは微妙に色味が違う。 ・・・が、個体差なのかよく見るとわずかに回転した状態で固定されてしまうようだったので ⇒ 若干回転はしているものの、撮影結果には影響しないと判断して使い続けることにした。 ■リンク ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08SM2Q1WP/ 」(Amazon) Amazonにて、2022,11,02注文⇒2022,11,03発送⇒2022,11,05受取。 本体900円+送料無料。新品。 | |||||||||||||||||||
| フラッシュ(ストロボ) | |
|---|---|
 |
左から、 ・ Canon SPEEDLITE 580EX II |
| Canon SPEEDLITE 580EX II | |
クリックして展開キヤノン製のアクセサリーシュー対応クリップオンストロボ。 その名の通り最大光量はガイドナンバー58で、大型ストロボに分類される。 同社のフラッグシップモデルであり操作性にも優れる。 電源は単三電池4本。 ■性能 フラッシュ調光補正のほか、FEB(いわゆるフラッシュブラケット)にも対応している。 580EXII本体のほかボディ側からでも設定できる。 対応する画角は24/28/35/50/70/80/105mmでオートズームが可能。 内蔵式のワイドパネルを展開することでさらに14mmの広角レンズにも対応する なおハイスピードシンクロに対応している。 大光量フラッシュらしく横位置・縦位置でのバウンス撮影に対応している。 キャッチライトパネルが内蔵されているためフラッシュ本体のみで全機能が使える。 また、-7°の俯角を付けることができ、至近距離での撮影でもムラになりにくい。 ■外観など 大部分がプラスティック製だが根元は金属製らしい。 設定内容は液晶モニターに表示されるのですぐに確認・変更ができる。 このモニターには適正露出となる距離の範囲が線形のメーターで表示されるため、 ガイドナンバーから逆算することなく適正露出が得られる範囲を確認できる。 充電状況はPILOTランプの「消灯⇒緑点灯(クイック発光可)⇒赤点灯(フル充電)」で確認できる。 このランプは押しボタンにもなっており、押すとテスト発光ができる。ただちょっと硬すぎて押しにくい。 また、PILOTランプの下には調光確認ランプが搭載されている。(撮影後に光るとイイらしい) ■購入メモ、リンク カメラのキタムラにて、2024,03,08注文・発送⇒2024,03,11センター発送⇒2024,03,12受取。 本体7,600円+送料550円。クーポン割引1,140円(本体価格の15%)。中古品C。 シンクロ端子の保護カバーが失われている。付属品なし。 ・ 「 https://canon.jp/corporate/newsrelease/2007/2007-02/pr-580ex2 」(公式ニュースリリース) | |
■EFマウント・フルサイズ
純正レンズにはほとんど同じ名前をしたマイナーチェンジモデルが多数存在する。(EF75-300mmなど)
単焦点レンズや望遠レンズはAPS-C機でも有用。ただし年代モノは解像力で見劣りするものも多い。
また、古いSIGMA製レンズの中にはROMの互換性問題により絞りが動かないものもあるため注意。
| SIGMA MINI ZOOM MACRO 28-80mm F3.5-5.6 ASPHERICAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前玉回転式
  |
|
|||||||||||||||
クリックして展開1996年ごろに発売された標準ズームレンズ。 LH603フードが取り付け可能。 ROMの互換性問題によりデジタル時代のカメラボディのほとんどで通信エラーが出てしまい、 エラーの出る機種では開放絞りでしか撮影することができない。いわゆる「デジタル非対応」。 ネット情報によると、かつてはROMの改修サービスが行われていたという。 ・ 「 http://akiophoto.com/photonote/101002lenscompatibility/ 」 ■購入メモ、リンク ヤフオクにて、2022,10,15落札⇒2022,10,17発送⇒2022,10,18受取。 本体500円+送料520円。中古品(動作未確認)。フロント・リアレンズキャップ付属。 AF不良あり。おそらくギア欠け。デジタル非対応。 ・ 「 https://web.archive.org/web/20030407044028/http://www.sigma-photo.co.jp/lense/28_80f35_56.html 」 ( 公式サイト。オリジナルは削除済みのためInternetArchiveのキャッシュ版。 ) ・ 「 https://www.awane-camera.com/2/4/sigma_af_28-80f35-56macro_nikon-af/index.htm 」(個人) | ||||||||||||||||
| SIGMA MINI ZOOM MACRO 28-80mm F3.5-5.6 II | ||||||||||||||||
前玉回転式
  |
|
|||||||||||||||
【歪曲収差検証】
広角端ではタル型収差、望遠端ではほぼ歪曲なし。ズームすると歪まなくなる素直な特性。 ・ 「 SIGMA 28-80mm F3.5-5.6 II 【お手軽!!歪曲収差検証】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | ||||||||||||||||
【色収差検証】
右上端1000x667pxから、月が写るように1000x100pxにトリミングしたもの。 広角端では大きな倍率色収差が見られる。望遠端で最小になるこれまた素直な特性。 ・ 「 SIGMA 28-80mm F3.5-5.6 II 【月面!!色収差検証】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | ||||||||||||||||
クリックして展開2001年ごろに発売された標準ズームレンズ。 時代が時代であるためフイルムカメラでのレビューも散見される。 シルバー・ブラックの二色展開でフード(LH640-01?LH670-01?)もあるらしい。[要出典] よほど売れたのか、現在は4,000円前後の中古品があらゆるサイトに出回っている。 だいぶ古いレンズながら写りはマトモでAFにも対応しているため、 おカネがない人や予備のレンズにオススメかもしれない。軽くて小さいのもポイントだろう。 ■光学性能 写りについては値段を考えればそれほど不満はない。ただし広角での倍率色収差はかなり大きい。 倍率色収差と歪曲収差はともにズームするほど軽減されていき、望遠端で最少となる。 このレンズは広角より望遠に重きを置いて設計されたものなのだろう。 マクロ撮影機能は80mm専用だが1:2で撮影できる。ただし手ブレ補正がない点に注意。 また、マクロOFFでも全域で最短撮影距離が50cmくらいであるためそこそこ寄れる。 当時のFAQには本機のマクロ性能について以下の記述がある。 MINI ZOOM MACRO 28-80mmF3.5-5.6、APO MACRO SUPER 70-300mmF4-5.6のマクロはスイッチで切りかえることにより、望遠側でフォーカスレンズをさらに繰り出して1:2の撮影倍率を得ていますが、マクロ専用のレンズと比べて歪曲収差等が大きく複写などにはあまり向きません。しかし、花や虫などをとっさに写したい時、マクロレンズに交換したり、クローズアップレンズを取り付けたりする間に、シャッターチャンスを逃してしまう可能性が高い時など、レンズ1本でズームからマクロまで撮影できる大きなメリットがあります。
つまり、マクロ撮影時の歪曲収差はあまりよろしくないらしい。
( 出典 : https://web.archive.org/web/20000711100750/http://www.sigma-photo.co.jp/faq/index.html ) とはいえSIGMAの言うように咄嗟の撮影には有効だろう。(マクロレンズ高いし・・・) ■外観など 鏡筒が最も短くなるのは45mmくらいの場所で、それ以上でもそれ以下でも伸びる。 フォーカスリングは無限遠で最も縮み、フォーカス位置を短くしていくと鏡筒も伸びていく。 上記の動きや分解記事の写真から2群ズームと思われる。 レンズがどういう動きをしているかぜひ覗いてみてほしい。 ■購入メモ、リンク ハードオフにて、2022,08,19注文・発送⇒2022,08,20受取。S/N2047516。 本体2,750円+送料1,000円。中古品Bランク。フロント・リアレンズキャップ付属。 ヤフオクにて、2022,10,11落札・発送⇒2022,10,13受取。S/N2038726。 本体550円+送料520円。中古品(故障品)。フロント・リアレンズキャップ、LH603フード(シルバー)付属。 AF時にAFモーターが空転してしまう模様。おそらくギア欠け。玉に異常はなし。 ・ 「 https://web.archive.org/web/20021208083817/http://www.sigma-photo.co.jp/lense/28_80f35_56_2.html 」 ( 公式サイト。オリジナルは削除済みのためInternetArchiveのキャッシュ版。 ) ・ 「 https://kakaku.com/item/10505010461/ 」 (価格.com) ・ 「 https://www.awane-camera.com/2/4/sigma_af_28-80f35-56macro_ii_sigma-sa/index.htm 」 (個人) | ||||||||||||||||
SIGMA LH603 レンズフード同社の28-80mmや28-90mmに装着できるとウワサのレンズフード。 ブラックとシルバーの2モデルの存在が確認できている。いずれも内面は黒のツヤ消し加工。 上の写真で装着しているレンズフードがまさにこれ。 実際に試してみたところ、28-80mm F3.5-5.6 II に取り付けることができた。 前向き・後ろ向きのいずれにも取り付け可能。カチッとは言わないが、ガタつきはなくしっかりハマる。 しかし、このレンズはピントリングにフードを取り付ける構造であるため、取り付け時に「AF」になっていると AF駆動用のギアに負荷がかかるだろう。そういえばフードが付いていた個体はAFが・・・あっ(察し) また、ピントリングに取り付けられていることからお察しの通り、 前玉が大きく繰り出される広角端・望遠端付近では効果が薄くなり、 特に80mmでのマクロ撮影はレンズフードから前玉がせり出すという奇妙な状態になってしまう。 ヤフオクにて、2022,10,11購入⇒2022,10,12発送⇒2022,10,13受取。 本体630円+送料520円。中古品。ブラック本体(2個)のみ。 | ||||||||||||||||
SIOTI 汎用レンズフード 広角 φ55mm
フィルター枠としてレンズに装着して使用する汎用レンズフード。レンズキャップ付属。 フィルター径が合うレンズであれば何にでも取り付けられるが、画角によってはケラレを生じる。 SIGMA・28-80mmに取り付けるため広角タイプを選んでいるが、 他のバリエーションとして中空タイプやロングタイプが存在するようだ。 なお、SIGMA・28-80mmではフルサイズ機で見てもケラレは確認されなかった。合格。 ■リンク ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07FSGZLQ3/ 」(Amazon) Amazonにて、2022,09,03購入。 本体999円+送料無料。新品。 | ||||||||||||||||
| SIGMA MINI ZOOM MACRO 28-80mm F3.5-5.6 ASPHERICAL HF | ||||||||||||||||
ヘリカルフォーカシング
  |
|
|||||||||||||||
クリックして展開2001年ごろに発売された標準ズームレンズ。 HF(ヘリカルフォーカシング)システムを採用したことで前玉が回転しなくなった。 レンズの枚数・群数や外寸は ”F3.5-5.6 II” と同じで、重量は ”HF” が10gだけ重くなっている。 専用フードはLH600-01。形状が円形から花形になったほか、取り付け位置も変更になっている。 価格.comのクチコミによると、2004年ごろに生産終了となったらしい。 ・ 「 https://bbs.kakaku.com/bbs/10505010460/SortID=3337390/ 」 ヤフオク等での流通量はHFと付かないモデルに対して圧倒的に少ないと感じられる。 もしかするとあまり生産数が多くないのかもしれない。これくしょんに最適だろう。 特徴的なヘリカルフォーカシングの内筒にはマクロモードで大きく繰り出した際に 撮影倍率の目盛りが見えるようになっている。 ■購入メモ、リンク ヤフオクにて、2022,10,11落札⇒2022,10,12発送⇒2022,10,13受取。 本体1,000円+送料1,040円。中古品(動作未確認)。フロントレンズキャップ付属。 LH600-01フード ・・・ ヤフオクにて2022,10,12落札⇒2022,10,15発送⇒2022,10,18受取。 本体1,280円+送料無料。中古品。 ・ 「 https://web.archive.org/web/20030417085805/http://www.sigma-photo.co.jp/lense/28_80f35_56hf.html 」 ( 公式サイト。オリジナルは削除済みのためInternetArchiveのキャッシュ版。 ) ・ 「 https://kakaku.com/item/10505010460/ 」 (価格.com) | ||||||||||||||||
| Canon EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM | ||||||||||||||||
インナーフォーカス
  |
|
|||||||||||||||
クリックして展開1998年に発売された標準ズームレンズ。シャッタースピード2段分を謳う手ブレ補正機能を搭載している。 フィルムカメラ時代から存在し、現在では中古品として数多く流通しており入手しやすい。 キヤノン製レンズで手ブレ補正を搭載するフルサイズ対応レンズとしてはおそらく最も安く手に入る。 専用フードはEW-78BII。切り欠きがないためカチッとはハマらない。 ■光学性能 古いレンズながら写りは全く問題なく、フルサイズ機と組み合わせれば感動的な解像力を発揮する。 しかし周辺減光は大きく、少し絞っても気になることもある。( ※DLO対応なのでDPPを使えば修正できる ) また、搭載しているISは古いせいか効きが弱めで動作音が大きい。 特にフルサイズ機向けの手ブレ補正機能付きレンズは軒並み高級品である中、 1万円と少しもあれば買えるこのレンズは、非常にコストパフォーマンスに優れていると言えるだろう。 周辺減光やISの効きが気になるならより新しく・より高いレンズをローンで買うしかない。 あるいはAPS-Cに逃げるか・・・。 ■外観など 外装はツルツルとしたプラスティック製で、正直すごく安っぽい。 なかなかにガタイが良く重さもあるため、割れてしまわないか心配になる。 全体のスタイルとしてはEFマウントレンズ群の伝統デザインとなっていて、 距離目盛は窓付きで、赤いラインで赤外線撮影時の指標も印刷されている。 これは個体差もあるかもしれないが、ズームリングがかなり渋く、それでいて自重で伸びてしまいやすい。 フィルター枠の大きさから分かる通り、前玉がなかなか立派なので少々フロントヘビーなのかもしれない。 というかマジでこのレンズデカすぎない・・・? F2.8のアレコレに比べればマシとはいえ・・・。 ■購入メモ、リンク 2ndstreetにて、2022,09,09注文・発送⇒2022,09,10受取。 本体7,590円+送料770円。中古品Bランク。フロント・リアキャップとフード(EW-78BII)が付属。 ・ 「 https://global.canon/ja/c-museum/product/ef342.html 」(公式サイト) ・ 「 https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/83280/~/【交換レンズ】ef28-135mm-f3.5-5.6-is-usm-製品仕様/ 」(公式サイト、MTFあり) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B00006I53S/ 」(Amazon) | ||||||||||||||||
| COSINA 28-210mm MC 1:4.2-6.5 ASPHERICAL IF | ||||||||||||||||
インナーフォーカス
 
( 撮影 : DMC-GH1 + Panasonic12-32mm ) |
|
|||||||||||||||
クリックして展開おそらく1999年発売の高倍率ズームレンズ。 先に入手していたFマウント版が懐かしかったので手に入れてみたが用途は未定。 若干レアかもしれない。 このレンズは(なぜか)情報が少ないため、ネット上には発売当時の記事は見つからない。 が、InternetArchiveで遡ると1999年にこのレンズが製品情報ページに追加されたことが分かる。 ・ 「 https://web.archive.org/web/19991011031548/http://www.cosina.co.jp/cosina/lenses.html 」 たぶん当時の雑誌等を漁れば情報は出るだろう。・・・面倒なのでやらないが。 ■光学性能 購入時、後ろから覗くと隅に小さなカビのようなものが見えるがクモリはなく、ゴミも少なかった。 Fマウント版のほうはかなりしっかりとクモリが出ていたので心配していたのだが・・・。 やはりクモリの発生は単なる経年劣化ではないのだろうか?湿度?紫外線? なんにしても長生きしてほしいものである。 ■外観など EFマウント版はモーター内蔵&絞りリングなしのため、レンズ付け根の部分が太くなっている。 マッスルカーのリアバンパーみたいでイマイチしっくり来ない。(変な例えだな・・・) モーターはおそらく普通のDCモーターで、レンズに触れているとはっきりとした振動を感じる。 専用フードは取り付け時の回転量が少なくカチッとも言わないが、 代わりにガタつきが少なくなっているため、比較的しっかりと取り付けできる印象。 ただし、レンズキャップが付いたままでは着脱できないため少々扱いづらい。 ちなみにこのフード、よく見ると左右方向に長い楕円形となっている。花形の中でも珍しいと思う。 実はピントリングがFマウントモデルと逆回りになっている。 ■購入メモ、リンク ヤフオクにて、2022,09,18落札⇒2022,09,19発送⇒2022,09,20受取。(台風14号で遅延しそうだった) 本体2,568円+送料870円。中古品。フロント・リアキャップとフードが付属。 ・ 「 https://web.archive.org/web/20040610015536/http://www.cosina.co.jp/cosina/seihin/2_super.html 」 ( 公式サイト。オリジナルはすでに削除済みのためInternetArchiveのキャッシュ版。 ) | ||||||||||||||||
| Canon EF75-300mm F4-5.6 II USM | ||||||||||||||||
前玉回転式
 
( 撮影 : DMC-GH1 + Panasonic12-32mm ) |
|
|||||||||||||||
【解像力検証】 APS-C 18MP
中心付近はどの焦点距離でも開放から使えるが、周辺部は絞っても微妙。 日の丸構図で活用しよう。 ・ 「 Canon EF75-300mm F4-5.6 II USM 【解像力検証APS-C・18MP】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | ||||||||||||||||
クリックして展開1995年に発売された望遠ズームレンズ。 後継モデルに「EF75-300mm F4-5.6 III USM」が存在する。性能的に近いモデルもいくつかある。 専用フードは円形フードの「ET-60」。 ■光学性能 写りは年代モノの割には悪くないと感じる。 ただし周辺部の解像力は焦点距離によらずあまり良くないようだ。 Canon純正レンズであるため、デジタルレンズオプティマイザ(DLO)を利用できる。 倍率色収差が結構目立つのでRAW現像時には活用しよう。 AFモーターには超音波モーター(USM)が採用されている・・・が、かなり遅い。 動く被写体を狙うのはだいぶ難しいと考えたほうが良いと思う。 ズームリングは回転式のため、(衝撃を加えたりしなければ)真上や真下を向いても保持できる。 ■外観など 外装はおそらくプラスティック製。質素なデザインとなっている。 内筒の先端付近にネジが露出している点はマイナスだろう。 ET-60フードはカチッとハマるのではなく少しギチギチに入るタイプ。 個体差かもしれないが、後ろ向きに取り付ける方が少し緩いようだった。 このフードは深さが5cmくらいあるので横から見るとコップのように見える。 ■購入メモ、リンク Amazonにて、2022,12,04注文⇒2022,12,08発送⇒2022,12,10受取。 本体6,480円+送料無料。中古品(良い)。ET-60フード、フロント・リアレンズキャップ付属。 ・ 「 https://global.canon/ja/c-museum/product/ef326.html 」(公式サイト) | ||||||||||||||||
| Tokina EMZ130AF 100-300mm F5.6-6.7 | ||||||||||||||||
前玉回転式 直進式ズーム
 
( 撮影 : EOS7D + EF-S18-55mmSTM ) |
|
|||||||||||||||
【解像力検証】 APS-C 18MP
300mmでは開放絞りだと球面収差の影響なのか画面全体で解像力が低い。 100/200mmなら中心付近は開放絞りから使える。絞ると水平解像度の1/2以上が使えるようになる。 ・ 「 Tokina EMZ130AF 100-300mm F5.6-6.7 【解像力検証APS-C・18MP】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | ||||||||||||||||
【歪曲収差検証】 APS-C
ズームするにつれて糸巻型収差が出てくる。 ・ 「 Tokina EMZ130AF 100-300mm F5.6-6.7 【お手軽!!APS-C歪曲収差検証】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | ||||||||||||||||
クリックして展開1990年代かそれ以前に発売された望遠ズームレンズ。1998年生産終了。 MF時代に流行した直進式ズームを採用しており時代を感じる。EFマウントモデルは少しレアかもしれない。 後継モデルは同じ焦点距離とF値ながら回転式ズームになった 「 EMZ130AF II 」 。 ただしEFマウントモデルは初代のEMZ130AFにしか存在しない。 ■光学性能 軸上色収差の影響でそれなりに絞らなければいけない点も不満である。 ・・・と、思っていたのだが、解像力を検証した結果EF75-300mmIIと比べてもそう悪くはなかった。 色収差もそこまでひどくもなく、開放F値が少々暗いものの写りだけで言えば割と優秀。 オートフォーカスにはDCモーターを用いているらしく、かなり古めかしいAF動作音を発する。 遠景であればそう悪くもないと思うが、被写体がだいぶ近い場合はAF精度がガバガバになる。 最短撮影距離は1.4mだが、AFの最短距離はもっと長いと思う。 直進式ズームであるため、真上を向くと鏡筒が縮み、真下を向くと鏡筒が伸びてしまう。 特に南中前後の月など大きく仰角を取らなければいけない場合は撮影が困難になる。 ■外観など 外装はツルツルとしたプラスティック製で高級感はない。内筒は金属製かもしれない。 ピントリングはチェッカリングで、グリップ(ズームリング?)は斜め向きの凹凸で滑り止め加工している。 おそらく直進式ズームでは回転方向にあまり力が加わらないためと思われる。 これは個体差かもしれないが、内筒を支えながらでないと壊れそうなくらいにフードの着脱が硬い。 内筒が少しガタつくこともあって壊してしまわないか、フードの着脱のたびに少しヒヤヒヤさせられる・・・。 ■購入メモ、リンク OFFモール(ハードオフ)にて、2022,11,08注文・発送⇒2022,11,09受取。 本体3,300円+送料1,000円。中古品Bランク。フード、フロント・リアレンズキャップ(リアはTAMRON製)付属。 ・ 「 https://www.tokina.co.jp/camera-lenses/support/terminate.html 」(修理対応終了リスト・公式サイト) | ||||||||||||||||
| 単焦点レンズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
左から、 ・ Canon EF24mm F2.8 ・ Canon EF50mm F1.8 II ( 撮影 : α7R + Samyang AF 35mm F1.8 )
SILKYPIX Pro11、フラッシュON | ||||||||
| Canon EF24mm F2.8 | |||||||||
| 【フィルター径φ58mm】 【手ブレ補正なし】 【寸法φ67.5x48.5mm】 【重量270g】 【リアフォーカス】 | |||||||||
クリックして展開com ■光学性能 com ■外観など com ■購入メモ、リンク com | |||||||||
| Canon EF50mm F1.8 II | |||||||||
| 【フィルター径φ52mm】 【手ブレ補正なし】 【寸法φ68.2x41mm】 【重量130g】 【全群繰り出し(直進)】 | |||||||||
【解像力検証】 APS-C 18MP
開放絞りではコマ収差の影響なのか特に周辺部の解像力が低い。 F5.6まで絞ると画面全体で素晴らしい解像力を発揮する。絞って使おう。 ・ 「 Canon EF50mm F1.8 II 【解像力検証APS-C・18MP】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||
【歪曲収差検証】
タル型収差。DLOで完全に補正できる。 ・ 「 Canon EF50mm F1.8 II 【お手軽!!歪曲収差検証】 - UAP14475 のブログⅢ 」 | |||||||||
【色収差検証】
右上端1000x667pxから、月が写るように1000x100pxにトリミングしたもの。 色収差はまったく見られない。F1.8で月がにじんで見えるのはコマ収差の影響。 ・ 「 https://uap14475.hatenadiary.jp/entry/2022/11/21/205014 」 | |||||||||
クリックして展開1990年に発売された単焦点レンズ。 フィルムカメラ時代から存在し、生産終了となった2022年現在でも中古品が多数出回っている。 もとより新品12,000円と低価格であったため、中古品なら状態が良くとも数千円で手に入れられる。 専用レンズフードとして「ES-62」が存在する。後継機種は「EF50mm F1.8 STM」など。(あちらはやや高価) 単焦点レンズは一般的に歪みが少なく写りが良いとされる。 一方、その名の通りズームが全くできないため構図決めが難しいなど取り回しはよくない。 そして複数の単焦点レンズを集めようとすればズームレンズ一本で済ませるよりもお金もかかる。 ■光学性能 開放F1.8とかなり明るいため、高速シャッターや大きなボケを容易に実現できる。 画質を最優先に考えるならF5.6以上が推奨される。この場合は画面全体で解像力が非常に高くなる。 歪曲収差はあるものの、色収差がほぼゼロなので純粋な「写り」という点でも高く評価できる。 とはいえ手ブレ補正付きのEF28-135mmが便利なので持て余しているが・・・。 かなり古いレンズではあるものの、デジタルレンズオプティマイザ(DLO)に対応しているため、 歪曲収差や周辺減光はボディ内補正やRAW現像で簡単に自動補正してもらえる。 ただしコマ収差についてはどうしようもないため、このレンズのネックであり続ける。 オートフォーカスにはDCモーターが用いられているようで、なかなか派手なギア音を発する。 なんとなくTOMIXを思い出すレンズなのであった・・・。 このレンズの最短撮影距離は0.45mでマクロモードもないため、 被写体にある程度近づいて撮りたい場合にはクローズアップレンズが必要になる。 ”STM”なら0.35m、”コンパクトマクロ”なら0.23mまで寄れるそうなのでよく比較検討しよう。 ■外観など 外装はツルツルとしたフルプラスティック製で、マウントもやはりプラスティック製。 かなり軽いことも相まって不安になるような安っぽさを感じてしまう。 とはいえこの軽さ・小ささはカメラバッグを圧迫しないため、持ち運びには非常に有利。 ちなみに製造国は個体によってJAPANであったりMALAYSIAであったりするという。 手元の個体はマウント面に 「 MADE IN MALAYSIA 」 と刻印されていた。 ■購入メモ、リンク カメラのキタムラにて、2022,09,01注文・店舗発送⇒2022,09,03センター発送⇒2022,09,04受取。 本体7,200円+送料(EOS5Dと同時購入)。中古品ABランク。 ・ 「 https://global.canon/ja/c-museum/product/ef295.html 」(公式サイト) ・ 「 https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/83985/~/【交換レンズ】ef50mm-f1.8-ii-製品仕様/ 」(公式サイト、MTFあり) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B00005K47X/ 」(Amazon) | |||||||||
Canon ES-62 + 62-L (レンズフード)
EF50mm F1.8 II に取り付けることができるレンズフード(ES-62)と専用アダプターリング(62-L)。 アダプターリングの溝にレンズフードを装着することで展開(前向き)・格納(後ろ向き)が可能。 アダプターリングはザラザラ仕上げの金属製で、フィルターが取り付けられるようにφ52mmのネジが切られている。 一方、レンズフードは爪までフルプラスティック製で少々安っぽい。ただし内面はキッチリとシボ加工されている。 レンズフードのツメがなぜかひっかかりやすいため、着脱には少しコツが必要。 着脱ボタンを強く押しこむのではなく、揉むように力を加えるとうまくいく・・・と思う。 たぶんプラスティック製だから強く押すと楕円形になってしまうのだろう。 着脱機構については改良の余地があるのではないだろうか・・・。 Amazonではオリジナルの半値程度でサードパーティー製品も売られている。 なお、中古品の中にはアダプターリング(62-L)が付属しないものもあるため注意が必要。 ■リンク ・ 「 https://cweb.canon.jp/ef/accessary/detail/2645a001.html 」(公式サイト) Amazonにて、2022,09,01購入・発送⇒2022,09,03受取。 本体2,298円+送料無料。新品。取扱説明書は入っていなかった。 (EF50mmのマニュアルに説明がある⇒「https://canon.jp/support/manual/ef/fixed-focal?pr=1687」) | |||||||||
■Qマウント
センサーサイズが1/2.3型または1/1.7型と非常に小さいため、
レンズ交換式カメラの中でもかなり小型軽量なシステムに仕上がっている。
| Pentax Q10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
||||||||||
クリックして展開2012年発売の1/2.3型イメージセンサー搭載ミラーレスカメラ。 4機種あるQマウントカメラの中では最後の1/2.3型センサー搭載機で、 後継の2機種はいずれも1/1.7型センサー搭載となっている。 M4/3やNikon1よりもさらに小さなセンサーサイズであるため容易にパンフォーカスを実現できる。 一方で小絞りボケが生じやすいほか高感度耐性も良くない。特性の把握が重要なカメラである。 なお、ボディキャップは他のマウントと異なりロック機構がなく、ハマってるだけとなっている。 しかも結構抜けやすい上に小さいので簡単に紛失できる。レンズを付けっぱなしにしておくべきだろう。 ■オートフォーカス、動画撮影 (評価中) ■背面液晶 (評価中) ■シャッター音
なおレンズシャッター非搭載レンズでの撮影時には電子シャッターになる。(レンズ持ってないので要検証) ■現像設定、購入メモ、リンク (評価中) | |||||||||||
| レンズ | |
|---|---|
 |
左から、 ・ Pentax 5-15mm F2.8-4.5 |
| Pentax 02 STANDARD ZOOM 5-15mm F2.8-4.5 | |
| 【フィルター径φ40.5mm】 【手ブレ補正なし】 【寸法φ48.5x48mm】 【重量96g】 【インナーフォーカス】 | |
クリックして展開2011年に発売された標準ズームレンズ。 レンズシャッターと内蔵NDフィルターを搭載している。 ■光学性能 (評価中) ■外観など (評価中) ■購入メモ、リンク Q10ボディの付属品として入手。 レンズフードはAliExpressで輸入した互換品・・・のはずだがオリジナルと見分けがつかないような・・・? ・ 「 https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/lens/q/high-performance/02-standard-zoom/ 」(公式サイト) | |
■Fマウント
レンズは S1 Pro を使っていたころ(2018年)に買ったもので、どれも元からカビなどがあり状態はイマイチ。
今や付けるボディすらなく、今後購入する予定もないのでインテリア雑貨と化してしまっている。
| TAMRON AF18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO (A14N) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インナーフォーカス
 
( 撮影 : DMC-GH1 + Panasonic12-32 ) |
|
||||||||
クリックして展開2005年に発売された高倍率ズームレンズ。 レンズ内がもうとにかくゴミだらけになっている。購入時からこうだったんだろうか。 このレンズは鏡筒がはしご車みたいに3段に伸びるので吸い込みやすいのかもしれない。 S1Proで撮影したうちの”よく撮れてる写真”は結構な割合でTAMRONで撮ったものだった。 ヤフオクにて、2018,08,17落札。 本体4,000円+送料不明。中古品。箱・取扱説明書・フード付き。 ■リンク ・ 「 https://www.tamron.co.jp/data/af-lens/a14.html 」(公式サイト) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B00768F2IY/ 」(Amazon) | |||||||||
| SIGMA MINI ZOOM MACRO 28-80mmD F3.5-5.6 II | |||||||||
前玉回転式
 
( 撮影 : E-PL6 + Panasonic12-32mm ) |
|
||||||||
クリックして展開EFマウントの28-80mmとほぼ同じ名前だが「D」が付いているモデル。標準ズームレンズ。 「D」付きがすべてそうなのかは不明だが、AFモーターが付いていない。 そのためボディ側にモーターが入っていない場合はMF専用になる。 微妙に損した気分になるレンズである。 レンズ内にゴミが多い。そしてピントリングと一緒に回る玉に菌糸状のカビが見える。 うまく後ろから覗くと顕微鏡で観察してるみたいにカビの発育状態が観察できる。 クモリはないから写りにはきっと影響しない・・・よね? S1Proで当時撮影した写真のEXIF情報を確認したところ、屋内撮影でよく使っていたようだった。 たぶん軽くて(同画角での)開放F値がほかの2本より少し小さいからだろう。 ヤフオクにて、2018,08,15落札。 本体4,000円+送料不明。中古品。フロントレンズキャップ付属。 | |||||||||
| COSINA 28-210mm MC 1:4.2-6.5 ASPHERICAL IF | |||||||||
インナーフォーカス
 
( 撮影 : EOS7D + EF-S18-55mmSTM ) |
|
||||||||
クリックして展開いつからか手元にある高倍率ズームレンズ。若干レアかもしれない。 公式サイトの中では「最短撮影距離は28mm時0.5m、210mm時で0.9m」としている。 購入時点でどうだったか忘れてしまったが、後ろのほうの玉にかなりクモリが出ている。 TAMRON・18-200mmやSIGMA・28-80mmと同じ場所に置いていたがコレにだけ出ている、 つまり私のせいではない・・・はず。それでも僕はやってない。 形は違うものの、カビはほかの2本にも生えているので私のせいかもしれない(自白) ”触れる部分に生えてるんなら取れるんじゃね?” とも思う・・・が、 それほど大々的に生えてるわけでもないので画質に大きな影響はないだろう。クモってるし。 ヤフオクにて、2018,08,12落札。(FUJIFILM FinePix S1 Pro とのセット) フード ・・・ ヤフオクにて2022,10,16落札⇒2022,10,17発送⇒2022,10,21受取(?)。 本体300円+送料200円。中古品。 ■リンク ・ 「 https://web.archive.org/web/20040610015536/http://www.cosina.co.jp/cosina/seihin/2_super.html 」 ( 公式サイト。オリジナルはすでに削除済みのためInternetArchiveのキャッシュ版。 ) | |||||||||
■カメラの墓
判定基準はテキトーだが基本的に「使い物にならない=死亡」である。
持っていても仕方のないものだが捨てるのはもったいない、よってまさに死蔵品と化している。
| Canon EOS 5D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
( 撮影 : E-PL6 + ? ) |
||||||||
クリックして展開2005年発売の35mmフルサイズイメージセンサー搭載一眼レフカメラ。 動画撮影機能やライブビュー機能が搭載されていない、古典的なスチルカメラ。 多少不便な分だけ中古品が安く手に入る・・・とはいえ3万円ほどする。 EOS10Dと異なり、「RAW+JPEG」を選択するとRAW(CR2)とJPEG(JPG)が別々に保存される。 小さな違いだが(専用ソフトウェアをインストールしていない機器から)パパッと確認したいときに便利。 EOS-1Dシリーズと同じくストロボが内蔵されていないため、必要ならホットシューに増設する必要がある。 プロ用の1Dはともかく、5Dはアマチュアも使う可能性があるわけだから正直付いていたほうが良かったと思う。 ストロボのない軍艦部のデザインはどこか物足りなさを感じる。(性能とは関係ないが・・・) 実は買ったはいいがあまり使っていないボディである。 フルサイズセンサーは屋外や暗所、動きの速い被写体に対しては非常に優秀な性能を発揮するのだが、 その反面、被写界深度があまりに浅く、屋内ではボケすぎてしまうことが扱いを難しくしている。 そしてレンズが高すぎる・・・。 ■シャッター音
■現像設定、購入メモ、リンク ピクチャースタイルは忠実設定にシャープネス+3、色合い+1としている。 ISO感度は800で常用。ISO1600も高速シャッター用には悪くない。屋外ではISO400。 自室で撮影する際はISO800、F5.6、SS1/15にしている。 2022,11,09に電源が入らなくなっていることが確認され、死亡が確定した。 現在はニコイチの材料として、ドナーの手配を待っている状態。わずか2ヶ月と少しの命であった。 カメラのキタムラにて、2022,09,01注文・店舗発送⇒2022,09,03センター発送⇒2022,09,04受取。 本体33,800円+送料550円。中古品ABランク。 ・ 「 https://global.canon/ja/c-museum/product/dslr791.html 」 (公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2005/11/17/2681.html 」 (デジカメWatch) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B000BEVDBK/ 」(Amazon) | |||||||||
Canon EP-EX15 (アイピースエクステンダー)
EOS10DやEOS5Dに取り付けることができるアイピースエクステンダー。 ファインダーの接眼部が15mm後方へ伸びる。カメラの背面に顔面を押し付けるストレスが軽くなる。 ただし、延長してもやはり当たるときは当たるほか、ファインダーの像が0.5倍になってしまいMFが困難になる。 また、突起が増えるため収納にも注意が必要。 非常に似た型番に「EP-EX15II」が存在するが対応機種が異なる。購入前に確認しよう。 ■リンク ・ 「 https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/2444a001.html 」(公式サイト) ヤフオクにて、2022,08,24落札。 本体1,280円+送料無料。中古品。EYE-Eb付属。(⇒EOS5D) ヤフオクにて、2022,08,27落札⇒2022,08,28発送⇒2022,08,30受取。 本体1,000円+送料185円。中古品(2個セット)。片方はわずかに錆びていた。EYE-Ebが1つ付属。 | |||||||||
| FUJIFILM FinePix S1 Pro | |||||||||
 |
( 撮影 : EOS5D + ? ) |
||||||||
クリックして展開2000年発売のAPS-Cサイズイメージセンサー搭載一眼レフカメラ。 動画撮影機能やライブビュー機能が搭載されていない、古典的なスチルカメラ。 ニコンと同じマウント、同じボディ(F60)を使用しているのにあえてコチラを選ぶならハニカム好きに違いない。 「記録画素数」は最大613万画素としているが、イメージセンサーの総画素数は340万画素しかない。 これは記録画素数が「ハニカム信号処理」によって画像を補間処理した結果から算出されるためである。 ・ 「 https://ja.wikipedia.org/wiki/スーパーCCDハニカム/ 」 ・ 「 https://www.wdic.org/w/CUL/スーパーCCDハニカム/ 」 残念ながら内部の何かしらがお亡くなりになった模様でエラー表示(FEE)が消えない。 以前からマウントの接触不良のような症状があったが、ついに死亡した。 最後の撮影が2019,08,08なのでその頃だろう。寿命わずか1年であった。 ヤフオクにて、2018,08,12落札。 本体8,800円+送料不明。中古品。ショルダーベルト、CFカード、電池型アダプター、COSINAレンズが付属。 ■リンク ・ 「 https://www.fujifilm.co.jp/news_r/nrj611.html 」(公式サイト) ・ 「 https://en.wikipedia.org/wiki/FinePix_S1_Pro 」(英語版Wikipedia) | |||||||||
| OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インナーフォーカス
 
|
( 撮影 : E-M1 + Panasonic12-32mm ) 色温度6500K +3 |
||||||||
クリックして展開2008年に発売された広角ズームレンズ。 ■光学性能 値段相応かもしれないが、正直なところもう少し写ることを期待していた・・・。 ⇒ 個体の不具合(片ボケ)が原因だと思われるため取り消し。 ■外観など (評価中) ■購入メモ、リンク カメラのキタムラにて、2023,03,11注文・発送⇒2023,03,12受取。 本体19,800円+送料550円。中古品B。おそらく完品。 2024,03,18、改めて過去の撮影結果を確認したところ、 購入当初から著しい片ボケを生じていたため、死亡判定とした。 つまりこのレンズは購入時点ですでに死んでいたのだ・・・。 ・ 「 http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/9-18_40_56/index.html 」(公式サイト・リンク切れ) ・ 「 https://www.olympus.co.jp/jp/news/2008a/nr080513zuikoj.html 」(公式ニュースリリース) | |||||||||
| TAMRON 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (B008E) | |||||||||
インナーフォーカス
 
( 撮影 : EOS7D + EF-S18-55mmSTM ) |
|
||||||||
クリックして展開2010年に発売された高倍率ズームレンズ。手ブレ補正機能を搭載している。 EOS7Dに取り付けると35mm換算で29-432mmとなり広角から望遠まで何でも撮れる。いわゆる”便利ズーム”。 専用フードはB008TS/B008/A18に対応する花形フードの「DA18」。 非常に近い型番に「B008TS」が存在する。基本性能はB008と同じだがコーティング等が変更されている。 また、B008の旧モデルとして同じ焦点距離とF値の「B003」が存在する。(色収差以外はB003のほうが優秀) 名前も見た目もそっくりさんだがレンズ構成から異なる。カムが外れることがあるらしい。 ■光学性能 写りは十分なものがあると思う。高倍率ズームにしては優秀と言えるだろう。 望遠端では周辺部の周辺減光が激しいが、解像力はそれほど悪くもないと思う。 また、某海外サイトによると歪曲収差が全域で2%程度あるらしい。少し大きいため注意。 色収差もちょっと大きい模様。広角端では少し気になるかもしれない。 搭載しているVC(手ブレ補正)は動作中に騒音が出るタイプ。効果はEF28-135mmよりは強い。 このレンズは高倍率ズームであるため、特に望遠側では役に立つ機会が多いだろう。 入手時より前から2枚目か3枚目あたりにカビのような点々が薄く広がっている。 これを取ろうと分解して前玉ユニットを水洗いしたところ浸水して一部にシミができた。(医療事故) 写りにそこまで影響はないようだが、非常に申し訳ない気分になった。 件のカビのような点々は接着剤の劣化かもしれない(要検証) なぜかAFが故障している個体が多い印象。PZD(圧電セラミックス)のせいなのだろうか? PZDは動作原理が違うからかやや甲高い動作音を発する。AF速度はまずまず。 ■外観など 高倍率ズームであるため鏡筒はかなり伸びる。 このはしご車並みの伸びっぷりの副作用なのか、ズームリングは重く、回転が渋いと感じる。 携行時にはズームロック機構を使うことで18mm(広角端)でズームリングを固定できる。 外装は他のTAMRON製品と同じくザラザラ塗装。なかなかイイと思う。 ■購入メモ、リンク リコレにて、2022,09,15注文⇒2022,09,16発送⇒2022,09,18受取。 本体5,980円+送料550円。中古品Eランク(ジャンク)。フロントレンズキャップ付属。 商品ページには「破損、打痕有り。カビ・バルサム切れ・ヒビ割れ。」と記載されていた。 レンズ内の大きなゴミが1つ、そして前玉ユニットにカビか劣化のようなものが確認できた。 2024,03,18、過去の実験中に負った浸水痕を原因として死亡判定。 厳密に言えばまだ普通に機能するが、使う気がしないので葬り去ってしまうことにした。 DA18フード ・・・ Amazonにて2022,09,18注文⇒2022,09,19発送⇒2022,09,21受取。 本体1,400円+送料無料。中古品。 ・ 「 https://www.tamron.co.jp/data/af-lens/b008/index.html 」(公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/452767.html 」(デジカメWatch) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/dp/B004FLJVXM/ 」(Amazon) | |||||||||
■マウントアダプター&テレコンバーター
電子接点を持たないものはAFや自動絞りが作動しないが、もちろんその分価格は安くなる。
| VILTROX JY-43F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
( 撮影 : E-M1 + Panasonic12-32mm ) 色温度6500K +3 |
||||||
クリックして展開OLYMPUS・MMF-1と同等の機能を持つマウントアダプター。純正品より安価に手に入る。 カラーバリエーションはブラックとシルバーの2色展開。 ■購入メモ、リンク Amazonにて、2023,03,11注文・発送⇒2023,03,12受取。 本体5,850円+送料無料。新品。 ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B082VW5VRS/ 」(Amazon) | |||||||
| K&F Concept MAF-M4/3 | |||||||
 |
( 撮影 : E-M1 + Panasonic12-32mm ) 色温度6500K +3 |
||||||
クリックして展開AマウントレンズをM4/3ボディに取り付けるためのマウントアダプター。 Panasonic製ボディで使用する場合は「レンズ無しレリーズ」をONにしておく必要がある。 わずかにバックフォーカスが長いのか、SIGMA8-16mmでは8-12mmの範囲で結像しなかった。 また、E-M1に取り付ける場合はM4/3レンズの取り付けに比べて回転が渋かった。 ■購入メモ、リンク Amazonにて、2023,03,02注文⇒2023,03,03発送⇒2023,03,04受取。 本体3,760円+送料無料。新品。 ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01172WOSK/ 」(Amazon) | |||||||
| Kenko DIGITAL TELEPLUS PRO300 1.4X DG | |||||||
 |
( 撮影 : E-M1 + Panasonic12-32mm ) 色温度6500K +3 |
||||||
クリックして展開レンズの焦点距離の1.4倍相当にまで像を拡大してくれるテレコンバーター。 像が大きくなる代わりにF値は1段分暗くなる。AFが効かなくなるレンズも多い。 同社のテレコンバーターであるMC4/MC7が50mmを基準に設計しているのに対し、 PRO300は300mmF2.8での使用を前提に設計されているらしい。 後継は「テレプラスDGX」シリーズ。 DGでは素通しだったExif情報がDGXならテレコンの効果を加味したもので記録されるという。 ■購入メモ、リンク カメラのキタムラにて、2022,12,08注文⇒2022,12,12発送⇒受取日不明。 本体4,400円+送料550円。中古品B。フロント・リアレンズキャップ、レンズポーチ付属。 | |||||||
| Kenko DIGITAL TELEPLUS PRO300 2X DG | |||||||
 |
( 撮影 : E-M1 + Panasonic12-32mm ) 色温度6500K +3 |
||||||
クリックして展開レンズの焦点距離の2倍相当にまで像を拡大してくれるテレコンバーター。 像が大きくなる代わりにF値は2段分暗くなる。AFが効かなくなるレンズも多い。 同社のテレコンバーターであるMC4/MC7が50mmを基準に設計しているのに対し、 PRO300は300mmF2.8での使用を前提に設計されているらしい。 後継は「テレプラスDGX」シリーズ。 DGでは素通しだったExif情報がDGXならテレコンの効果を加味したもので記録されるという。 ■購入メモ、リンク カメラのキタムラにて、2022,12,08注文⇒2022,12,12発送⇒受取日不明。 本体3,600円+送料(1.4Xテレコンと同梱)。中古品B。レンズリアキャップ付属 | |||||||
■フィルター
| クローズアップレンズ | |
|---|---|
|
最短撮影距離を短縮するフィルター。No.1/2/3/4/5/10があり、番号が大きいほど効果が強い。
このフィルターを使ってマクロ撮影を行う場合は周辺部の画質が大きく低下する。 もとから接写に重きを置くマクロレンズであればこういうことは少ないらしいが・・・。 追加でマクロレンズを買うのは厳しい、けど近くを撮りたい、そんなときに活躍するフィルターである。 | |
クリックして展開手元にはあるのは以下のもの。 ・ HAKUBA CF-CU467 MCクローズアップ No.4 φ67mm ・ HAKUBA CF-CU152 MCクローズアップ No.1 φ52mm ・ Kenko MC クローズアップレンズ No.1 φ55mm 355718 ・ MARUMI クローズアップレンズ MC+1 φ72mm 031127 クローズアップレンズはカメラ用の老眼鏡と考えれば良い。 これを使えば近くが見える(=ピントが合う)ようにはなるが、遠くは見えなくなる。人間用と同じである。 特に効果の強いものほど最大撮影距離が縮んでしまい、フォーカス範囲がかなり狭くなる。 そのため、あまりに強力なものを選んでしまうと使いづらいと感じるかもしれない。(私もそうでした・・・) クローズアップレンズ装着時の最短撮影距離はkenkoいわく、 レンズの最短撮影距離×クローズアップレンズの焦点距離 レンズの最短撮影距離+クローズアップレンズの焦点距離 で計算できるらしい。(「https://www.kenko-tokina.co.jp/lp/close-up-lens/」) 一眼レフカメラの最短撮影距離は「イメージセンサーから〇cm」と表記されるため、 No.1(33cm)やNo.2(25cm)でもレンズ先からの距離で言えば結構な近さまで寄れる。 なお、φ72mmなどフィルター径の大きなものはレンズ面がせり出していることがあるため注意。 ( 私は早速ど真ん中にキズを入れてしまいました・・・ ) 色収差を補正した高級タイプもkenkoから発売されているらしい。 ■リンク ・ 「 https://www.hakubaphoto.jp/category/260400/ 」(HAKUBAの公式サイト) Amazonにて、2018,08,14購入。本体991円+送料無料。新品。(HAKUBA・No.4・φ67mm) Amazonにて、2022,09,03購入。本体1,042円+送料無料。新品。(HAKUBA・No.1・φ52mm) Amazonにて、2022,09,09購入。本体1,139円+送料無料。新品。(MARUMI・No.1・φ72mm) Amazonにて、2022,11,10購入。本体1,115円+送料無料。新品。(Kenko・No.1・φ55mm) | |
| レンズプロテクター | |
|
レンズの前玉を保護してくれるフィルター。光学的には何の意味もない。
ただし、あまりにいい加減なものを使うとフィルターの反射が撮影に影響することがある。 低反射率や防汚コートを謳う製品であれば付けっぱなしでも気にならないが、値段は高い。 | |
クリックして展開手元にはあるのは以下のもの。 ・ HAKUBA SMC-PRO φ55mm ・ HAKUBA SMC-PRO φ58mm (⇒Canon・EF-S18-55mm) ・ HAKUBA SMC-PRO φ67mm (⇒TAMRON・17-50mm(A16S)) ・ HAKUBA SMC-PRO φ72mm (⇒TAMRON・17-50mm(B005E)) ・ HAKUBA MCレンズガード φ37mm シルバー (⇒Panasonic・12-32mm) マルチコーティングが施されたレンズプロテクター。 SMC-PROは反射率0.5%(公称値)、MCレンズガードは反射率1.5%(公称値)。 像がほとんど暗くならないので付けっぱなしでも気にならない、優秀なレンズプロテクター。 ・ Kenko PRO1D プロテクター φ37mm シルバー (⇒OLYMPUS・14-42mm) マルチコーティングが施されたレンズプロテクター。 反射率0.5%(公称値)。SMC-PROと近い性能だが若干お値段が高い。 ・ Amazon Basics CF26-N-67 UV保護 φ67mm UVカットができると謳うフィルター。しかしレビューではただのガラス疑惑が出ている。 UVカット効果が本当にあるのかはさておき、保護フィルターは万が一の際にレンズを損傷から守ってくれる。 ただし、このAmazonフィルターは付けると少しだけ像が暗くなる。気になる人は要注意。 ■リンク ・ 「 https://www.hakubaphoto.jp/category/260101 」(HAKUBA公式サイト) ・ 「 https://www.kenko-tokina.co.jp/discontinued/filters/protect/4961607252512.html 」(Kenko公式サイト) ・ 「 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00XNMX4EG/ 」(AmazonBasics) Amazonにて、2022,09,03購入。本体789円+送料無料。新品。(Amazon・φ67mm) Amazonにて、2022,10,01購入。本体888円+送料無料。新品。(HAKUBA・φ37mm) Amazonにて、2022,10,01購入。本体2,629円+送料無料。新品。(HAKUBA・φ72mm) Amazonにて、2022,11,02購入。本体2,253円+送料無料。新品。(HAKUBA・φ58mm) Amazonにて、2022,11,10購入。本体1,596円+送料無料。新品。(HAKUBA・φ55mm) Amazonにて、2023,02,01購入。本体2,222円+送料無料。新品。(HAKUBA・φ67mm) Amazonにて、2023,03,04購入。本体1,036円+送料無料。中古品(良い)。(Kenko・φ37mm) | |
書き込み速度があまりに遅いメモリーカードを使っていると連写時の待ち時間が長くなるほか、
再生画面に画像が表示されるまでの時間が伸びたりする。とにかく速いの買っとけ!
| WesternDigital SiliconDrive 1GB PATA (SSD-C01G3565) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
 |
( 撮影 : α57 + SAL1855 ) |
||||
クリックして展開WesternDigital製のコンパクトフラッシュ。詳細が全く分からない謎多きメモリーカードである。 Yahoo!検索で画像を探すと、裏面側のラベルに製造日が2007年と記載されているものが見つかった。 「SiliconDriveII」も存在するようだ。 転送速度はあまりよろしくない。産業向けなのだろうか? ヤフオクにて、2018,08,18落札。 本体600円+送料不明。中古品。 | |||||
| Sandisk Extreme コンパクトフラッシュカード | |||||
 |
( 撮影 : α57 + SAL1855 ) |
||||
クリックして展開Sandisk製のコンパクトフラッシュカード。上位モデルに「Extreme Pro」が存在する。 カメラの連写性能に影響する書き込み速度は公称85MB/s(16GBのみ60MB/s)。 コンパクトフラッシュの中でもかなり速い部類に入るだろう。 しかし性能以上に金ピカのラベルが印象的ではないだろうか。 EOS7Dに装備中。 ■リンク ・ 「 https://web.archive.org/web/20160204144523/http://www.sandisk.co.jp/products/memory-cards/compactflash/ 」(公式サイト。オリジナルは削除済みのためInternetArchiveのキャッシュ版。) ヤフオクにて、2022,09,03落札。 本体3,000円+送料210円。中古品。 | |||||
| Sandisk Extreme Pro コンパクトフラッシュカード | |||||
 |
( 撮影 : α57 + SAL1855 ) |
||||
クリックして展開Sandisk製のコンパクトフラッシュカード。おそらく最上位モデル。 カメラの連写性能に影響する書き込み速度は公称150MB/s(256GBのみ140MB/s)。 UDMA7の理論値(166MB/s)とほぼ同じ転送速度を発揮する、最強のコンパクトフラッシュ。 しかしラベルが金ピカではなくなってしまった点は残念。 EOS5Dに装備中。 ■リンク ・ 「 https://web.archive.org/web/20160204144523/http://www.sandisk.co.jp/products/memory-cards/compactflash/ 」(公式サイト。オリジナルは削除済みのためInternetArchiveのキャッシュ版。) ヤフオクにて、2022,09,07落札。 本体3,200円+送料無料。中古品。 | |||||
■思い出のコンデジ
携帯性に優れるためそれほどカメラにこだわりのない人にも人気があったが、
スマートフォンの普及により建築現場等の一部を除いて市場が縮小したとされる。
最近はどれもほとんど使用していないが、せっかくなのでここに書き残しておきたい。
| Canon IXY DIGITAL 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
( 撮影 : NEX-6 + SIGMA30mm(A013) ) |
||||||||
クリックして展開2004年発売の1/2.5型CCDイメージセンサー搭載カメラ。 かなり長く愛用していたが、2022年になって写りに満足できなくなりお役御免となった。 ■オートフォーカス、動画撮影 動画撮影はほぼほぼオモチャなので期待するべきではない。 ■ファインダー、背面液晶 さすがに年代モノなだけあって液晶画面はかなり小さく画質も粗い。(2.0型) 光学式ファインダーも搭載しているが、パララックスが生じるため慣れが必要。 ■シャッター音 (評価中) ■現像設定、購入メモ、リンク 小学生のころに父から貰ったもの。 ・ 「 https://global.canon/ja/c-museum/product/dcc504.html 」(公式サイト) ・ 「 https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/10665/~/【コンパクトデジタルカメラ】デジタルカメラixy-digital-50機種仕様/ 」(公式FAQ) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2004/10/29/331.html 」(デジカメWatch) | |||||||||
| SONY Cyber-shot T110 | |||||||||
 |
( 撮影 : NEX-6 + SIGMA30mm(A013) ) |
||||||||
クリックして展開2011年発売の1/2.3型イメージセンサー搭載カメラ。 ボタンやスイッチがほとんど廃されており、操作は主にタッチパネルで行うことになる。 IXYの後継として購入したものの気に入らなかったため使わずじまいとなってしまった。 見た目は気に入っているのだが・・・。 ■オートフォーカス、動画撮影 (評価中) ■ファインダー、背面液晶 (評価中) ■シャッター音 (評価中) ■現像設定、購入メモ、リンク セカンドストリート(通販)にて、2022,08,12注文⇒2022,08,13発送⇒受取日不明。 本体6.490円+送料770円。中古品B。 「Marine Pack」(防水プロテクター)が付属した。だが沈める勇気を持てずにいる・・・。 ・ 「 https://www.sony.jp/cyber-shot/products/archive/DSC-T110/ 」(公式サイト) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/420040.html 」(デジカメWatch) | |||||||||
| FUJIFILM FinePix F300EXR | |||||||||
 |
( 撮影 : NEX-6 + SIGMA30mm(A013) ) |
||||||||
クリックして展開2010年発売の1/2型スーパーCCDハニカムEXRイメージセンサー搭載カメラ。 F200EXRの後継にあたる機種・・・のはずだがセンサーサイズが小型化されてしまった悲しきカメラ。 T110の代わりとして購入したものの光軸ズレ(片ボケ)が出ていたので使わないことにしてしまった。 なぜ返品しなかったかと言えば、不良なのか欠陥なのかが分からなかったから。 しかしよく触ってみるとズームレバーも反応がおかしく、左端まで倒すと反応しなくなるようだ。 やっぱり壊れてるじゃないか(憤怒) ■オートフォーカス、動画撮影 (評価中) ■ファインダー、背面液晶 (評価中) ■シャッター音 (評価中) ■現像設定、購入メモ、リンク セカンドストリート(通販)にて、2022,08,16注文⇒2022,08,17発送⇒受取日不明。 本体6.490円+送料770円。中古品B。 ・ 「 https://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/articleffnr_0414.html 」(公式ニュースリリース) ・ 「 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/400283.html 」(デジカメWatch) | |||||||||
■思ったこと
個人の感想なので(このセクションに限りませんが)非常に主観的です。
| 総評系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センサーサイズごとの利点と欠点ネット上ではフルサイズ派・APS-C派・M4/3派の三つ巴の戦いが続いている――― そこで私なりにセンサーサイズごとの利点と欠点を書いておこうと思います。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPS系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[TIPS] MTFの読み方と分かることカールツァイスの古い資料が非常に詳しく有用なためご一読を推奨します。 ・ 「 https://web.archive.org/web/20160424000919/https://www.zeiss.com/content/dam/Photography/new/pdf/en/cln_archiv/cln30_en_web_special_mtf_01.pdf 」 まず、MTFには多くの場合、以下の4つの情報が表示されます。 ・ サジタル(S)方向・10本/mm ・ メリジオナル(M)方向・10本/mm ・ サジタル(S)方向・30本/mm ・ メリジオナル(S)方向・30本/mm 「サジタル方向」のMTF値は放射状の縞模様を撮影した場合のコントラストを、 「メリジオナル方向」のMTF値は同心円状の縞模様を撮影した場合のコントラストを表しています。 なお、メリジオナル方向はタンジェンタル方向と表記されることもあります。 M4/3レンズの場合は20本/mmと60本/mm(または40本/mm)で表示されます。 これは35mmフルサイズセンサーに比べて辺方向で1/2程度の大きさしかないM4/3センサーでは、 同等の解像感を得るために2倍の空間周波数に対応する必要があるためでしょう。 考え方は様々あると思いますが、私は30本/mmだけ見てればOKだと思ってます。 そもそも10本/mmがそこまでひどいレンズは少なく、解像力を測るには空間周波数が低すぎるためです。 解像力が高いレンズ=優れたレンズ、私はそう思っています。 MTFのグラフを変化させる主な要因は結局のところ「諸収差」になります。 もし、収差の全くないレンズがあったとするならMTF曲線はほぼ直線になってしまうでしょう。 では諸収差がMTF曲線をどのように変化させるか、というとおそらく以下の通りです。
また、倍率色収差と歪曲収差はデジタル補正によって修正することが可能ですが、 このような処理を行った場合は以下のような影響がおそらくあります。
歪曲収差補正は実質的に画像の引き伸ばしであるのでMTFは悪化します。 このため、いかにデジタル補正があると言っても、元の歪曲収差があまりに強烈なレンズの場合、 歪曲収差を補正すると解像感が非常に悪くなってしまう可能性があります。 結局のところ、良好なMTFを得るためには良好な光学設計が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[TIPS] 動画撮影に関してPモードやAモードでは、特に明るい場所での動画撮影時に フレームレートを大きく上回るシャッタースピードが設定される場合がある。 このような設定で撮影された動画はパラパラ漫画のような仕上がりになってしまう。 これを防ぐためには動画撮影時に「シャッタースピード優先」モードを選択し、 シャッタースピードをフレームレートと同じ数値(60fpsなら1/60秒)に設定して撮影する。 これによって画面の動きがスムーズに繋がり、滑らかな動画が撮影できるようになる。 ミラーレスであれば上記のような設定が可能だが、一眼レフの場合はPモードしか選べないことが多いほか、 ミラーレスであってもマウントアダプター使用時などにはPモードのみに制限されることもある。 もし、動画撮影に力を入れるのであれば、ミラーレスボディ+ミラーレス専用レンズ、と揃える必要があるかもしれない。 ただし、ミラーレスであっても一眼ムービーらしい「ボケを生かした撮影」を行う場合は、 絞りを開くために撮影モードを「M」に設定し、必要に応じてNDフィルターを取り付けなくてはならない。(面倒) ■リンク ・ 「 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25003704/ 」 (価格.com) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[TIPS] オリンパスのカメラ事業売却(2020年)オリンパスは2020年にカメラ事業を売却し、現在はOMデジタルソリューションズ株式会社に引き継がれている。 みんなもっとカメラを買おう(提案) ■リンク ・ 「 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60765810V20C20A6000000/ 」 (日本経済新聞) ・ 「 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2006/24/news141.html 」 (ITmedia NEWS) ・ 「 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2007/02/news075.html 」 (ITmedia NEWS) ・ 「 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001231937/SortID=23491991/ 」 (価格.com) ・ 「 https://kakakumag.com/camera/?id=15631 」 (価格.comマガジン) ・ 「 https://www.cipa.jp/j/stats/dc.html 」 (CIPAによる統計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■便利なリンク集
・ 『 http://www.photozone.de/reviews 』
いろんなレンズのレビューが掲載されているサイト。全文英語。
ディストーションやMTFを独自に計測してくれているため非常に参考になる。
・ 『 https://www.lenstip.com/lenses_reviews.html 』
上のphotozoneと同じく、ディストーションやMTFを独自に掲載してくれているサイト。全文英語。
お値段をPLNで示していることがあるのでポーランドと縁があるのかもしれない。
・ 『 https://aska-sg.net/maker_int/index.html 』
各メーカーの”中の人”にインタビューした記事シリーズ。
文字化けするためブラウザから文字エンコーディングを変更する必要がある。(Shift-JIS?)
・ 『 収差| Sport Optics Guide|株式会社ニコンビジョン 』
ニコンによる各種収差に関する解説。非常にわかりやすい。
前提は双眼鏡だがカメラにも通用する知識なのでぜひ予習しておこう。
・ 『 カメラのしくみって? | キヤノンサイエンスラボ・キッズ | キヤノングローバル 』
キヤノンによるカメラの仕組みの解説。実物の写真を用いているため分かりやすい。
サイト名に”キッズ”と付いてはいるが、大人にとっても非常に有益なサイトである。
■便利なリンク集(お買い物用)
・ 『 【カメラのキタムラ】デジカメ・ビデオカメラ・プリンター等の通販 』
CMでもおなじみのカメラ専門店・・・のはずだが最近はカメラ以外もいろいろ扱っている模様。
全国各地の店舗在庫から取り寄せが可能。ただし配送スケジュールがやや特殊なので注意。
さすがに専門なだけあって在庫が多く、探しやすさも上々。ただ付属品や状態の書き方がたまにガバガバ。
全体的に商品価値のある程度高いものが多い印象。あまりに古いものは少ないと感じる。
・ 『 カメラ|オフモール - 中古通販のハードオフ公式サイト【オフモ】 』
リユース品販売店。専門店ではないもののボディもレンズも結構扱っているようだ。
キタムラとは対照的にもはや情報すら出てこないような激古レンズやジャンク品も多い。
検索やジャンル分けがガバガバなため、写真と説明文をよく見て間違いがないか確認する必要がある。
また、送料は商品や店舗によってだいぶ差があるので注意。
・ 『 カメラ(カメラ)検索結果|中古品の通販サイト セカンドストリートオンラインストア 』
リユース品販売店。品ぞろえはOFFモールに近いが数が少ないと感じる。
そして検索画面から読み取れる情報が非常に少ない(写真のみ)ため選びにくい。
一応、検索窓にマウント名(「EFマウント」など)を入れるとある程度は絞れる。
・ 『 リコレ! | ビックカメラグループ ソフマップの中古通販サイト【公式】 』
ソフマップの中古品専門サイト。レンズもボディもそこそこ出入りがあるようだ。
百万円オーバーの美品から数千円のジャンクまで幅広く扱っている。あまりに古い製品は少ない。
特にジャンク品は状態表記が大雑把で、画像もキズ・カビ・クモリの確認にはあまり役に立たない。
マウントごとのジャンル分けは正確で探しやすい。
・ 『 Amazon | 本, ファッション, 家電から食品まで | アマゾン 』
みんな知ってる・何でも売ってるAmazon。もちろんカメラボディやレンズも扱っている。
併設のAmazonマーケットプレイスでは中古品もかなり出品されている。ジャンク品相当のものもある。
Amazonが販売する商品、またはFBAを利用している出品であれば返品の手続きも非常にラク。
ただし、マーケットプレイス出品は商品画像がかなり小さく、状態の確認が難しい。
また、カメラ関連の取引はヤフオクでもかなり活発である。
ボディキャップやアイピースエクステンダーといった細かなパーツも出品されている。
しかし、あまりに高額な商品(ボディやレンズ)を個人間取引で売買するのはオススメしない。
■撮影機材
・ ここに載ってるいずれか
■更新履歴
OLYMPUS君が旧製品情報を全消ししたがURL張り直しは面倒だ。
というわけでここに貼ってしまおう。なおMTF曲線等は見れない模様。ガバガバCSR
「 https://jp.omsystem.com/product/lens/record/index.html 」(交換レンズ)
「 https://jp.omsystem.com/product/dslr/record/index.html 」(カメラボディ)
2022,10,xx (クリックして展開)
・ 2022,10,13 21:21
「SIGMA 28-80mm F3.5-5.6 II MACRO」を「SIGMA MINI ZOOM MACRO 28-80mm F3.5-5.6 II」に変更。
Fマウントモデルも同様に変更。そしてEFマウントモデルを追加で1本入手したので追記。
「SIOTI レンズフード 広角 φ55mm」は「SIOTI 汎用レンズフード 広角 φ55mm」に変更。
・ 2022,10,14
E-PL6、SIGMA・28-80mm(EF)、OLYMPUS・14-42mmの写真を更新。
LH603とPanasonic・12-32mmの項を追加。「もくじ」の枠が500pxから550pxに拡幅。
「インナーフォーカス」でないレンズに「前玉回転式」や「全群繰り出し(直進)」の表示を新設。
EFマウントレンズとM4/3レンズに「寸法・重量」の情報を追加。更新履歴をdetailsタグで折り畳み化。
・ 2022,10,15 20:17
Panasonic・12-32mmのパープルフリンジの件を追加。やはり実地試験は重要だな・・・。
・ 2022,10,18 20:27
SIGMA・28-80mmIIの全体像の写真を更新。初代とHFに関する記述をそれぞれに移動。
SIGMA・28-80mm(初代)とSIGMA・28-80mmHFを追加。三兄弟は白い厚紙を敷いたうえで撮影。
今回からE-PL6はISO800、F5.6、SS1/15にセットして撮影している。
TAMRON・18-270mmのDA18フードの入手について追記。
2022,11,xx (クリックして展開)
・ 2022,11,05 01:01
EFレンズのリストをAPS-C専用とフルサイズ対応で分離。
SIGMA・28-80mmIIとEF50mmIIの歪曲収差を掲載。
・ 2022,11,10 23:02
EF-S18-55mmSTM と Tokina・100-300mm を追加。
ページ上部に掲載している作例を皆既月食の写真に変更。
作りかけ感がありありとした出来になってしまったので近日更新予定。
・ 2022,11,14 21:06
作例に掲げていた写真の輝点が気になっていたので修正。
ついでに旧作例のタイトルをsammaryタグで表示するようにした。
クローズアップレンズとレンズプロテクターを買い足したので追加した。
クローズアップレンズの「クリックして展開」に掲載していた写真(EF50mmIIに装着したところ)を取り除いた。
・ 2022,11,15 19:49
レンズ全体の写真は1500x1000px、それ以外は600x400px、JPEG品質は一律80にすることにした。
( 参照 : 「 https://uap14475.hatenadiary.jp/entry/2022/11/15/190801 」 )
EOS5D、EOS7D、E-PL6、EF-S18-55mm、LH-63C、SIGMA28-80mm三兄弟、Tokina100-300mm、
Olympus14-42mm、Panasonic12-32mmの写真を圧縮。
R-F-3、EP-EX15、SIOTI、ES-62の写真を2枚から1枚にした。
LH603の写真を取り除いた。
更新履歴を月ごとに分割した。
・ 2022,11,15 20:53
S1Pro、EOS10D、R-F-3、EP-EX15、ES-62の写真を圧縮。
S1Proはモノクロからカラーに変更。素材は同じながら加工はやり直している。
11/9にEOS5Dが死亡していた件を追記。
・ 2022,11,15 21:04
作例をすべて非表示にした。気に食わなかったのではなく、単純に重いため。
いつかまとめて記事にしてしまおう。ちなみに例の福岡大学の工事現場は現在立派なプールとなっている。
トップに掲げている写真の旧作はURLで表示することにした。あわせてdetailsタグを撤去。
・ 2022,11,23 00:07
もくじのEOS5Dに【死亡】を追加。S1ProとEOS5Dの項目にも追加。
SIGMA28-80mmIIに【色収差検証】を追加。
・ 2022,11,24 21:49
はてなブログの仕様変更があったのか、勝手にpタグが追加されるようになってしまった。
そのため一部の表示が乱れるかもしれない。せっかくのmarkdownが台無しだぁ・・・
E-PL6の手ブレ補正は録画中でなくともムービーモードであれば常時作動するようだったので修正。
同時に「[TIPS] 動画撮影に関して」を追加。割とマジで私も悩んでいたので書き残しておきたかった。
もくじが長くなるため[TIPS]については表示しないことにした。
Tokina100-300mmに色収差検証の結果を掲載。
Panasonic12-32mmとOlympus14-42mmに色収差補正の参考値を追加。(いずれも広角端のみ)
リンク先にAmazonを追加。
内容が重要なため2022,10,10の更新履歴のみdetailsタグから除外し折りたたまないようにした。
・ 2022,11,26 08:02
EF50mmIIに色収差の検証結果を掲載。
Panasonic12-32mmに12mm以外の色収差補正の参考値を追加。
感想文として「思ったこと」の項目を追加。内容が薄い。
・2022,11,27 08:31
EF50mmIIの写真を更新。圧縮方法は新基準(Q80)。新たに入手したDMC-GH1の初仕事。
・ 2022,11,27 09:57
EF28-135mm、COSINA28-210mm、EF50mmIIの写真を更新。DMC-GH1使用。
EF50mmIIの写真はSilkypixSEからコントラスト(調子)を「標準」から「硬調」に変更しただけ。
・ 2022,11,27 17:30
DMC-GH1を追加。「[TIPS] PCでのRAW現像に関して」も設置。
SIGMA18-50mmの写真を更新。
・ 2022,11,28
TAMRON17-50mmに「[TIPS] 色収差&歪曲収差補正(GIMP2.8)」を設置。
Panasonic12-32mmとOlympus14-42mmの収差補正について加筆。
・ 2022,11,30 22:16
DMC-GH1にデジカメWatchの参考URLを追加。「[TIPS] PCでのRAW現像に関して」を刷新。
TAMRON17-50の写真を更新。現像設定を新たにしたDMC-GH1が出動。
同レンズの「[TIPS] 色収差&歪曲収差補正(GIMP2.8)」を刷新。
2022,12,xx (クリックして展開)
・ 2022,12,01 20:34
TAMRON17-50mmのTIPS内で「50mm」とするべきところが「17mm」となっていたため訂正。
・ 2022,12,01 22:45
TAMRON18-270の写真を更新。今回はEOS7DとEF-S18-55mmSTMで出動。
TAMRON18-270とSIGMA18-50mmに写真を撮影した構成を表示。将来的にはサンプルを兼ねる計画。
更新履歴のborder-bottomを分離して、追加のdiv要素のborder-topにした。細かなことだが・・・。
・ 2022,12,01 23:02
DMC-GH1のTIPSに記載のRAW現像レシピを更新。コントラストを下げた。
・ 2022,12,02 22:31
DMC-GH1の3:2での解像度を追記。コメント部分も少し変更。
TAMRON17-50mmの写真を更新。コメント部分も変更。
SIGMA18-50mmの写真を更新(現像設定を変更)。コメント部分も変更。
EF-S18-55mmSTMとLH-63Cの全景の写真を更新。イケメンに見える向きで撮り直した。
同時にEF-S18-55mmSTMのコメントを大幅拡充。
TAMRON18-270mmのコメント部分を更新。
レンズ編(EFマウント・フルサイズ対応)のコメント部分を変更。
「屋内での撮影が多いことから手ブレ補正付きの標準ズームを主力としている。」としつつ
手ブレ補正の入ったレンズを一つも持っていないという矛盾に気付いたため。
EFマウント・フルサイズ対応レンズすべてのコメント部分を更新。
Tokina100-300mmの写真に撮影情報を追加。
Fマウントレンズの写真をすべて更新。撮影情報も追加。
M4/3レンズの写真に撮影情報を追加。コメント部分も更新。
・ 2022,12,03 11:31
TAMRON18-270の外装が金属かプラか判断付かないのでプラ製との記述を削除。
Tokina100-300mm、Panasonic12-32mmのコメントを少し更新。
・ 2022,12,03 20:09
DMC-GH1のRAW現像設定について追記。ナチュラルシャープは悔い改めて♰。
・ 2022,12,03 22:39
Tokina100-300mmに歪曲収差の検証結果(APS-C)を追加。
・ 2022,12,05 17:51
Olympus14-42mmの収差補正について追記。
Olympus40-150mmの項目を追加。写真は後で。
・ 2022,12,05 21:20
EF50mmII、Cosina28-210mmの写真を更新。撮り直しと同時に現像設定を変更。
Olympus40-150mmRの写真を掲載。
・ 2022,12,15 23:25
α57、SAL1855を追加。同時にAマウントレンズのリストを追加。
「もくじ」からアクセサリーの項目を削除。すっきりして見やすくなった。
すべてのカメラボディの項目に「シャッター音」の欄を追加。
DMC-GH1のコメントを編集。
「思ったこと」の体裁をフィルター編同等のものに変更。
・ 2022,12,17 11:00
EOS7D、E-PL6のコメントを更新。
α57のコメントを少し更新。「[TIPS] PCでのRAW現像に関して」を新設。
EF75-300mmIIを追加。最近曇りばかりでテストできてない。
EMZ130AFのコメントを少し更新。やっぱり直進式ズームは・・・ね?
AマウントレンズにAFモーターの有無の表示を追加。
SAL1855のコメントを更新。まあキットレンズだから・・・。
メモリーカード編を新設。とりあえずコンパクトフラッシュ3枚だけ掲載。
・ 2022,12,18 23:34
EOS7D、E-PL6のコメントを少しだけ加筆。
DMC-GH1、α57のコメントに加筆。RAW現像についても加筆。
・ 2022,12,19 22:09
EF-S18-55mmSTMに歪曲収差の検証結果を掲載。
・ 2022,12,19 22:41
もくじの脱字を修正
SIGMA18-50mmに歪曲収差の検証結果を掲載。
・ 2022,12,19 23:26
TAMRON17-50mmに歪曲収差の検証結果を掲載。
・ 2022,12,25 15:39
メリークリスマス!
EF-S18-55mmSTMに解像力検証の結果を掲載。
TAMRON17-50mm、SIGMA18-50mm、EF-S18-55mmの歪曲収差検証の結果を強化イメージタイプに差し替え。
EMZ130AFのAPS-C検証分の見出しを分かりやすくした。
・ 2022,12,29 00:09
EF-S18-55mmSTMの解像力検証と歪曲収差検証の体裁を変更。
・ 2022,12,30 21:31
α57の現像設定(色調)について追記。
TAMRON18-250mmを追加。
2023,01,xx (クリックして展開)
・ 2023,01,03
ハッピーニューイヤー!
TAMRON17-50mmVCに解像力検証の結果を掲載。歪曲収差検証は体裁を変更。
EF-S18-55mmSTMの解像力検証の体裁をTAMRON17-50mmのものに合わせた。
・ 2023,01,04 22:38
SIGMA8-16mm、TAMRON17-50mm(A16S)、MINOLTA500mmを追加。
マジで項目を追加しただけなので内容は後日拡充する予定。
・ 2023,01,05 20:07
TAMRON17-50mm(A16S)の撮影情報を間違えていたので修正。
・ 2023,01,05 23:01
TAMRON17-50mm(B005E)、LH-63Cのコメントを少し変更。
TAMRON17-50mm(A16S)に解像度検証の結果を掲載。コメントも加筆。
MINOLTA500mmのコメントを加筆。
・ 2023,01,06 20:44
EF75-300mmIIに解像力検証の結果を掲載。
・ 2023,01,07 19:53
EF75-300mmIIのコメントを少し変更。
EMZ130AFに解像力検証の結果を掲載。あわせてコメントも変更。
SIGMA8-16mmの写真を更新。どうも気に入らなかったので2枚とも撮り直した。
・ 2023,01,08 18:44
MINOLTA500mmに解像力検証の結果を掲載。あわせてコメントも変更。
・ 2023,01,09 20:03
TAMRON17-50mmVC(B005E)の「色収差&歪曲収差補正(GIMP2.8)」について、
Fix-CAは解像度によって数値を変える必要があるようだったのでその旨を追記。
EF50mmIIに解像力検証の結果を掲載。
・ 2023,01,21 20:00
SIGMA18-50mmに解像力検証の結果を掲載。歪曲収差検証の体裁を変更。
EF-S18-55mmSTMとSAL1855の写真を更新。
2023,03,xx (クリックして展開)
・ 2023,03,08 23:26
トップ画像を『満月』に更新した。月ばっかりで申し訳ない。
ボディ編とレンズ編を統合し、マウント・フォーマット別に再編した。
あわせて「もくじ」を改良、マウントごとの説明文も変更した。
・ 2023,03,08 23:51
detailsタグを展開すると表示が崩れる問題を修正。(ボディとレンズで別々のtableタグにした)
・ 2023,03,09 22:21
各マウントの説明文を更新。
・ 2023,03,09 23:36
カメラボディの情報表示を刷新。(とりあえずEOS10DとEOS7Dのみ)
ISO感度とライブビューの項目を削除、シャッター音はdetailsタグ内へ移設。
写真の表示サイズは幅300pxから幅200pxへ変更。
・ 2023,03,10 20:35
EOS10DとEOS7Dの情報表示を更新。寸法・重量を表示するようにした。他のボディも追々更新予定。
「思ったこと」のリンクが間違っていたので修正。そして同セクションを大きく刷新。
E-PL6の下に付いていたTIPSも「思ったこと」に移設した。
・ 2023,03,10 21:37
EOS10D/EOS7D以外のカメラボディの情報表示を更新。新スタイルになった。
Olympus・E-M1を追加した。写真や説明文は後日追加する。
・ 2023,03,11 17:48
「[TIPS] MTFの読み方と分かること」を追加。書きかけ。
・ 2023,03,11 20:00
Olympus・E-M1と「[TIPS] MTFの読み方と分かること」に追記。
・ 2023,03,11 22:34
レンズプロテクターを買い足していたので追記。
・ 2023,03,14 21:05
「[TIPS] 歪曲収差補正・簡便法(GIMP2.8)」をSIGMA8-16mmとTAMRON17-50mm(A16S)に追加。
SIGMA8-16mmにはさらに「【歪曲収差検証】」も追加。WBが気に入らなかったので写真も更新した。
今後は写真の下に撮影情報としてWB設定も載せることにした。(特に色温度で指定した場合)
・ 2023,03,14 21:28
TAMRON17-50mm(A16S)に「【歪曲収差検証】」を追加。はてなフォトライフを漁ったらすでにうpされていた。
ついでにAF時のモーター音がうるさいことを追記。これはレンズのせいというよりボディのせいだとは思うが・・・。
・ 2023,03,15 22:38
SAL1855に「【歪曲収差検証】」を追加。
・ 2023,03,16 20:29
SAL1855とPanasonic12-32mmに「【解像力検証】」を追加。
Panasonic12-32mmとOlympus14-42mmの歪曲収差補正は「自動」で十分と思ったので修正。
・ 2023,03,16 21:33
EOS7D、EOS5D、α57、E-PL6、DMC-GH1のシャッター音の記述を更新または追加。
・ 2023,03,16 22:28
EOS10DとEOS5Dの解説部分の体裁を他のボディと同じにした。
ついでにSIGMA8-16mmのAmazonへのリンクを追加。
・ 2023,03,17 21:10
α57の現像設定について追記。ISO100は屋外でよく使うので。
・ 2023,03,21 12:25
「フォーサーズマウント」と「マウントアダプター&テレコンバーター」を追加。
「フィルター編」を「フィルター」に、「メモリーカード編」を「メモリーカード」に改名。
EOS7Dの説明を少しだけ更新。
E-M1の写真を追加。
・ 2023,03,21 12:39
E-M1の写真のホワイトバランスが気に入らなかったので差し替え。
・ 2023,03,21 15:31
ZD9-18mmの飾り板の写真で背景を間違えていたので差し替え。
テレコンバーターは「テレプラスDGX」ではなく「テレプラスDG」だったので修正。
MAF-M4/3とテレプラスDG2種の写真を掲載。
・ 2023,03,21 16:23
1.4xテレコンの説明が間違っていたので修正。
2023,10,xx (クリックして展開)
・ 2023,10,06 00:09
もくじをオシャレに更新。本文・もくじセットでマウントの並びを変更した。
新たにEマウントを追加。NEX-6、Zeiss12mm、SIGMA30mm(A013)を追加(ただし写真なし)。
M4/3にSIGMA19mm(A013)を追加した(ただし写真なし)。
単焦点レンズには「単焦点」の表示を付加した。
・ 2023,10,09 02:16
E-M1の写真を貼り替えた。
NEX-6の写真を追加した。
NEX-6、Touit12mm、SIGMA30mm(A013)の説明文を加筆修正。
・ 2023,10,11 02:57
M4/3とFTのレンズから「センサー」の欄を除去した。そもそもセンサーサイズが1つしかないうえに、
SIGMA19mm(A013)のような他マウント(APS-C)にも対応するレンズの表現が難しいため。
あわせて写真の撮影情報の記載位置も移動させた。
NEX-6の写真のホワイトバランスがイマイチだったのでRAW現像をやり直して差し替えた。
SIGMA19mm(A013)、Touit12mm、SIGMA30mm(A013)の写真を追加した。
・ 2023,10,19 00:38
「思い出のコンデジ」を新設。IXY、T110、F300EXRの3機を掲載。
NEX-6にシャッター音の記述を追加。他の部分にも細かな修正を行った。
・ 2023,10,25 23:31
アイキャッチ画像を更新。EOS7DからE-M1になった。
Touit12mm、SIGMA30mm(A013)の写真を更新。向きが変わった。
Touit12mmは全体はE-M1、飾り板はNEX-6で撮ったものになったが、撮影機材の表記はE-M1撮影とした。
2024,01,xx (クリックして展開)
・ 2024,01,31 06:00
もくじを更新。関連するマウントごとに点線で区切った。
新たにFEマウントを追加。α7Rを追加。ただしひな形のみ。
「Eマウント」を「Eマウント・APS-C」とし、フォーマットサイズで区分することにした。
Eマウント・APS-Cのレンズを「単焦点レンズ」として分類した。
Eマウント・APS-Cのボディ・レンズの写真を差し替えた。
レンズの飾り板の写真は廃止。ボディは操作系が見えるように背面を撮るようにした。
・ 2024,01,31 22:26
Eマウント・APS-Cの項目を見やすくデザインし直した。
Eマウント・APS-CのNEX-6とレンズの写真を更新した。
2024,02,xx (クリックして展開)
・ 2024,02,01 06:21
Qマウントを追加。Q10と5-15mmF2.8-4.5を掲載。
・ 2024,02,01 22:51
もくじのQマウント(Pentax)とFマウント(Nikon)が同じグループになってたので修正。
「Eマウント」となっていた部分を「Eマウント・APS-C」に変更。
マイクロフォーサーズの項目をEマウントと同じ新様式に変更。写真も更新。
M4/3のレンズはズームレンズと単焦点レンズの2種類に区分した。
・ 2024,02,03 07:06
EF24mmF2.8を追加。ただしひな形のみ。
EF24mmとEF50mmIIを「単焦点レンズ」に分類した。
EFマウント・フルサイズの「単焦点レンズ」の写真を掲載した。
NEX-6とEマウント「単焦点レンズ」の写真を更新した。
・ 2024,02,05 23:01
α7Rの写真を追加し、文章を書き込んだ。
・ 2024,02,05 23:09
アイキャッチ画像が古くなっていた(掲載していないものになっていた)ので変更。
E-M1をアイキャッチにしていたが、最近OMDSに元気がないのでα7Rにした。
α7Rの文章の一部がコメントアウトになっていたので修正。
・ 2024,02,09 22:19
α57、EOS10D、EOS7Dの写真を更新。
「SIGMA SD1 Merrill EFマウント改造型」を追加。
・ 2024,02,28 22:38
多忙につき掲載できていないレンズ数本を「もくじ」に【掲載予定】として表示。
M4/3にはMeike3.5mmとLaowa6mm、FEマウントにはSamyang35mm、
EFマウントにはSigma8-16mm(APS-C)とSigma12-24mm(フルサイズ)、
マウントアダプターにはEF-NEXを表示した。
なおLaowaとSamyangはまだ手元に届いていない。
・ 2024,02,28 23:34
もくじ内のリンクが正常に貼れていなかったので修正。
2024,03,xx (クリックして展開)
・ 2024,03,19 01:11
「カメラの墓」を新設。死亡判定を受けたカメラボディとレンズを集約した。
クリップオンストロボを「フラッシュ(ストロボ)」と分類してマウントごとに掲載した。
現時点では「3600HS(D)」、「ADP-MAA」、「580EX II」の3つを掲載している。
レンズの項目に付いている見出し部分の文字色と背景色を変更した。
・ 2024,03,19 04:18
580EXIIがもくじに載っていなかったので修正。
580EXIIの仕様に関する記述に誤りがあったので修正。
3600HS(D)の名称を細かく修正。
もくじにPanasonic35-100mmとPanasonic100-300mmを【掲載予定】として表示。
もくじの「お気に入り」表示を更新。数が減った。
M4/3マウントのコメント部分をわずかに修正。
・ 2024,03,19 07:54
EF/EF-Sマウント・APS-Cのレンズ項目の体裁を新しくした。写真も更新した。
LH-63Cフードの説明文に加筆した。だって白いフードかっこいいもん!
EFマウント・フルサイズの単焦点レンズの写真を新しくした。
・ 2024,03,19 09:00
もくじを微調整した。
・ 2024,03,19 12:43
Meike3.5mmとLaowa6mmを掲載した。Laowa6mmはさっき届いたばかり。
マイクロフォーサーズの単焦点レンズの写真を差し替えた。
・ 2024,03,20 08:43
Panasonic35-100mmとPanasonic100-300mmを掲載した。
M4/3のズームレンズを「パナソニック軍団」と「オリンパス軍団」に分類した。
M4/3のズームレンズの写真を更新した。
・ 2024,03,21 12:32
SamyangAF35mmF1.8を掲載した。同時にFEマウントに「単焦点レンズ」の項を設けた。